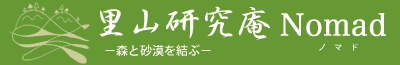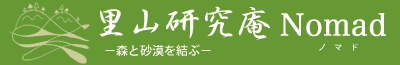東日本大震災から半年が経って 東日本大震災から半年が経って
21世紀未来像の欠如と地域再生の混迷
― 上からの震災復興を許す土壌 ―
2011年9月18日
小貫雅男
伊藤恵子
(加筆・改訂2011.9.22)
■全文のPDFダウンロード(201KB、A4用紙20枚分)
☆緊急提言「東日本大震災から希望の明日へ」はこちらへ!
はじめに
東日本大震災から今日で半年が過ぎた。私たち自身の社会が長い歴史の積み重ねの中で抱えてきた思想的・理論的負の遺産についても、いよいよ本格的に目を向けていかなければならない時に来ている。
一九世紀、偉大なる時代の変革者たちにとって、歴史観の探究とその構築(歴史学研究)は、経済学研究の導きの糸であった。その意味で、歴史観の構築と経済学の研究は、紛れもなく車の両輪となっていたのである。
こうした包括的で全一体的な研究の成果から自ずと導き出された一九世紀の未来社会論は、一九世紀から二〇世紀に生きる人々にとって、それがどんな結末をもたらしたかは別にしても、その行く手を照らし出す光明となって、確かにある時期までは夢と希望と目標を与え、現実世界を動かす力となっていたことは、間違いのない歴史的事実であろう。
二〇世紀も終わり二一世紀の今、私たちは、3・11の巨大地震と巨大津浪、東京電力福島第一原子力発電所の大事故という未曾有の大災害を境に、社会が大きく転換する時代の奔流の真っ直中に立たされている。精彩を失ったかつての未来社会論にかわる21世紀の私たち自身の新たな未来社会論を今なお探りあぐね、人々は、不確定な未来と現実の混沌と閉塞状況の中で、明日への希望を失っている。まさに今日、二一世紀を貫き展望するに足る未来像の欠如こそが、東日本大震災の被災地の復興のみならず、日本のすべての地域再生の混迷※ にさらなる拍車をかけ、そこに生きる人々を諦念と絶望にさえ陥らせようとしている。この地域の現実と労働の現場に気づかなければならない。私たちは、いつ止むとも知れぬ暴風雨の荒れ狂う大海を羅針盤なしの航海を続け、さ迷っているといっても過言ではない。
こうした時代認識に立つ時、新たな未来社会論の構築に先立って、今、何よりも切実に求められているものは、新たな歴史観の探究である。それはとりもなおさず、大自然界の摂理に背く核エネルギーの利用という事態にまで至らしめた、一九世紀以来の近代主義的歴史観に終止符を打ち、二一世紀の時代要請に応えうる新たな歴史観を探究することであろう。そして、新たに構築される歴史観と、そこから自ずと導き出される新たな経済学ならびに「地域研究」とを両輪に、21世紀の未来社会論は確立されていくのである。この探究の道のりは、たやすいものではないが、自然、社会、人文科学の諸分野の垣根を越えた真摯な対話によって、道は次第に拓かれていくにちがいない。
それにしても、大自然界と人間社会をあらためて統一的に捉え直そうとするならば、宇宙、地球、生命の存在とその生成・進化を貫く自然界の「適応・調整」(=自己組織化)の原理が、私たち人間社会にも、その普遍的原理として基本的には貫徹していると見なければならない。
しかし、人類は大自然の一部でありながら、他の生物には見られない特異な進化を遂げ、ある歴史的段階から人間社会は、自然界の原理とはまったく違った異質の原理、つまり「指揮・統制・支配」の原理によって動かされてきたことに気づかされる。人間社会の業の深さを思い知らされるのである。
今こそ広大無窮の宇宙の生成・進化の歴史の中で、あらためて自然と人間、人間と人間の関係を捉え直し、私たち人間の存在形態を根源から問い直す必要がある。そして、市場競争至上主義「拡大経済」下の今ではすでに常識となっている現代賃金労働者という人間の存在形態とは、一体いかなるものであるのか、生命の淵源を辿り、人類史という長いスパンの中でもう一度、その性格と本質を見極め、その歴史的限界を明らかにしなければならない。現代賃金労働者という人間の存在形態を暗黙の前提とする近代の思想と人間観が、当初の理念とは別に、現実生活において結局は人々をことごとく拝金・拝物主義に追いやり、人間の尊厳を貶め、人間の生命を軽んじてきたとするならば、今こそそれを根本から超克しうる「生命本位史観」※※ ともいうべき二一世紀の新たな歴史観の探究に着手しなければならない時に来ている。
その新たな歴史観の探究は、まさに諸学の革新の大前提となるべき学問的営為であるが、その状況は、時代が求める切実な要請からはあまりにも遅れていると言わざるをえない。しかし、この営為を抜きにしては、今日求められている本当の意味でのパラダイムの転換はありえないのである。
私たちは、分野の別を問うことなく、まずはできるところから取り掛かり、ひたむきに試行錯誤を重ねていかなければならない。このことが、今、私たちに突きつけられた差し迫った課題となっている。
ところで、私たちが生きている現代社会は、分かり易く単純化して言うならば、家族、地域、国、グローバルな世界といった具合に、多重階層構造を成している。最上位の階層に君臨する巨大資本が、あらゆるモノやカネや情報の流れを統御支配する。そしてそれは、それ自身の論理によって、賃金労働者という人間の存在形態を再生産するとともに、同時にその存立基盤そのものをも徹底的に切り崩しつつ、この巨大システムの下位基礎階層に位置する家族や地域の固有の機能を撹乱し、衰退させていく。このことが今や逆に、この多重階層システムの巨大な構造そのものを土台から朽ち果てさせ、揺るがしている。
人間社会の基礎代謝をミクロのレベルで直接的に担うまさにこの家族と地域の再生産を破壊する限り、人間社会の巨大な構造は、決して安定して存在し続けることはあり得ない。そうだとすれば、社会の大転換期にあってはなおのこと、経済成長率指標偏重のこれまでの典型的な「経済学」の狭い経済主義的分析では、こうした現代社会の本質をより深層からトータルに把握することは、ますます困難になっていくに違いない。
私たちは今、このことに気づかなければならない。こうした時代の変革期に差しかかっているからこそなおのこと、現代社会のこの巨大な構造の下位基礎階層に位置する家族や地域から出発して、それを基軸に社会を全一体的に考察する「地域研究」の必要性と重要性は、いよいよ大きくなってくると見なければならない。
では、そもそも「地域」とは、そして「地域研究」とは一体何なのであろうか。今、あらためて考え直さなければならない時に来ている。
「地域」とは、自然と人間の基礎的物質代謝の場、暮らしの場、いのちの再生産の場としての、人間の絆によるひとつのまとまりある地理的、自然的基礎単位である。この基礎的「地域」は、家族によって構成され、多くは伝統的な集落の系譜を引き継ぐものである。人間社会は、家族、基礎的「地域」、さらにいくつかの階梯を経てより広域へと次第に拡張しつつ、多重・重層的な階層構造を築きあげている。
人間とその社会への洞察は、とりとめもなく広大な現実世界の中から、任意に典型的なこの基礎的「地域」を抽出し、これを地域モデルに設定し、長期にわたり総合的に調査・研究することによってはじめて深まる。
現代は、世界のいかなる辺境にある「地域」も、いわゆる先進工業国の「地域」も、グローバル化の世界構造の中に組み込まれている。こうした時代にあって、自然と人間という二大要素からなる有機的運動体であり、歴史的存在でもあるこの「地域」を、ひとつのまとまりある総体として深く認識するためには、(1)「地域」共時態、(2) 歴史通時態、 (3)「世界」場という、異なる三つの次元の相を有機的に連関させて、具体的かつ総合的に考察することがもとめられる。こうすることによって、社会全体を、そして世界をも、全一体的にその本質において具体的に捉えることが可能になる。やがてそれは、社会経済の普遍的にして強靱な理論に、さらには二一世紀世界を見究める哲学にまで昇華されていく。「地域研究」は、こうして、二一世紀の未来社会をも展望しうる方法論の確立にむかうものでなければならない。
こうした主旨からすれば、本来、「地域研究」は、諸学の寄せ集めの単なる混合物であるはずもない。だとすれば、それは、まさに時代が要請する壮大な理念のもとに、自然、社会、人文科学のあらゆる学問領域の成果の上に、事物や人間や世界の根源的原理を究める諸科学の科学、つまり、二一世紀の新たな哲学の確立と、それに基づく歴史観を導きの糸に、相対的に自律的な独自の学問的体系を築く努力がもとめられてくる。こうして確立される新しい「地域研究」は、二一世紀未来社会を見通す透徹した歴史観を新たな指針に、混迷する今日の現実世界に立ち向かっていくことになろう。
グローバル経済が世界を席捲し、家族を、そして地域を破局へと追い込んでいる今こそ、グローバル化への対抗軸として、何よりもまず、私たちの生命活動を直接的かつ基礎的に保障している家族と地域の再生を急がなければならない。そのために今、何をなすべきかが問われている。時代のこの大きな転換期にふさわしい包括的で新しい「地域研究」の確立と、「地域実践」の取り組みがもとめられているのである。
※ 震災復興の混迷とその背景については、後掲「緊急提言・東日本大震災から
希望の明日へ」(小貫雅男・伊藤恵子、2011年4月23日)の全文を参照のこと。
※※『菜園家族21』(小貫・伊藤、コモンズ、2008年)の第2章第3節「自然の
摂理と“菜園家族”」(61〜72ページ)の項目「自然界を貫く“適応・調整”
原理」、「自然法則の現れとしての生命」、「自然の原理に適った週休五日制
のワークシェアリング」、「二一世紀“高度自然社会”への道」に詳述。
3・11大震災に際しての「緊急提言」
二〇一一年三月十一日、東北・関東を襲った巨大地震と恐るべき巨大津波、そして、福島原発の大事故は、私たちが日常に安住し抱いてきたこれまでの幸福感や人生観、さらには自然観や社会観をはじめ、科学・技術のあり方に至るすべての観念をもことごとく打ち砕いた。
一八世紀イギリス産業革命にはじまる近代とは、成長を前提にした時代である。したがって、実に長きにわたって多くの人々の心を捉えていたものは、「成長はいいこと」、「ゼロ成長などとんでもない」、ましてや「脱成長なんてあり得ない」という考えであった。
3・11は、この近代の成長神話を根底からくつがえす、実に衝撃的な出来事であった。まさに私たちは、3・11によって近代文明の終焉への大きな分水嶺に立たされた。これまでの価値観の大転換なしには、もはや生き延びることができない時点に差しかかっていることを知らなければならない。今となっては、せめてもこの自覚が、そして自粛の念が一時的なものに終わらないことを切に願う。
あれから半年が過ぎた。あの悲惨なあまりにもむごい災難を忘れたかのように、あるいは、あらゆる巧妙な手を使って忘れさせようとしながら、またもや市場競争至上主義「拡大経済」の奥底に潜む得体の知れない巨大な怪物が息を吹き返し、頭をもたげて蠢きはじめている。こうした動きに打ち克ち、ひとりひとりが自己の意識を変革し、いかにその状況に対抗する軸を確立できるのか。新たな理念のもとに、被災地の真の復旧・復興ができるかどうかは、長い至難の道のりではあるが、このこと如何に大きくかかっていると言ってもいいであろう。
つまり、被災地復興の問題は、被災地の当事者だけに限られたことではなく、まさに私たち自身の未来のゆくえを真剣に考えることである。震災からほぼ一ヵ月が経った四月二三日、緊急提言「東日本大震災から希望の明日へ ―大地に生きる人間復活の道は開かれている―」(小貫雅男・伊藤恵子、二〇一一年四月二三日)を取り急ぎまとめようと思い立ったのは、そのためである。
私たちは、特にここ十年来、滋賀県の琵琶湖に注ぐ犬上川・芹川の最上流、鈴鹿山中の限界集落・大君ヶ畑に「里山研究庵Nomad」という拠点を定め、彦根市・多賀町・甲良町・豊郷町の一市三町を含むこの森と湖を結ぶ流域地域圏を地域モデルに、日本の農山村地域とその中核都市の調査・研究に取り組んできた。このたびの未曾有の事態に直面し、歴史の大きな岐路にある今、奥山にあって、「地域研究」の立場から、ささやかながらも何かを発信したいと思い、この「緊急提言」をホームページで公開してきた。
本稿では、この「緊急提言」の目次を、まずはその概要にかえて紹介しておきたい。
―「緊急提言」の目次 ―
はじめに (2)
「原発安全神話」の上に築かれた危うい国 (5)
生産と消費と暮らしのあり方を根本から変える (7)
緊急を要する生活再建 (9)
地域復興の基軸に家族をおく ― 家族の再生なくして復興なし (11)
復興は上からではない ― 市町村の人々が主体に下から上へ積み上げる (13)
従来の常識をくつがえし、今こそ独創的な財源捻出を! (14)
誰のための復興構想なのか (17)
にわか仕込みの復興構想私案 ― その典型 (19)
続々と現れる復興への目論見 (22)
復興構想私案の震源地はここにあり (25)
財界の意を汲む復興構想の末路 (28)
未来社会を展望し得る論究の欠如とそれがもたらす弊害 (31)
弱さを克服し新たな基本理念の確立を (33)
3・11からの復興は21世紀日本のかたちを決める (34)
むすびにかえて ― 北国、春を待つ思い (36)
★「緊急提言」の全文は、里山研究庵Nomadホームページ
http://www.satoken-nomad.com/ にPDFファイルで公開、A4用紙23枚分。
この「緊急提言」の趣旨のご理解に資するよう、冒頭からごく一部を抜粋し、以下に転載しておく。
「原発安全神話」の上に築かれた危うい国
私たちはこれまで市場競争至上主義「拡大経済」の延長線上に、化石エネルギーとそれに代わる「夢のエネルギー」原子力に下支えされた文明にしがみつき、経済の発展とよりよい暮らしを際限なく求めてきた。しかしそれは、ことごとく裏目に出た。長い歴史の中で培われてきた人間の絆は分断され、地域コミュニティは衰退し、「無縁社会」という、実に人類史上まれに見る異常事態を現出させた。人間にとって本源的な農林漁業を衰退させ、農山漁村の超過疎・高齢化とともに、都市部への人口集中と巨大都市の出現を許し、それを放置してきた。
今や東京への一極集中に対する不安と恐怖も、いよいよ現実のものになってきた。今回の大震災時に発生した首都圏での交通麻痺や「計画停電」、放射能の拡散、水・食料・その他生活必需品の買い込みによる混乱状況からも、多くの人々がその恐ろしさをひしひしと実感したはずだ。首都圏直下型や東海、東南海、南海地震が起きたら、そのパニック状態は計り知れないものがある。
経済成長の日陰となった僻地に原発を集中させ、遠隔地の大工業地帯や巨大都市の電気需要を賄う電力供給システムは、「原発安全神話」を喧伝し、住民を欺きながら構築されていったものである。このたびの巨大地震と津波と福島原発による複合災害は、東北地方に広がる農林漁業の基盤に壊滅的な打撃を与えたばかりでなく、人間のいのちに、そして長い歴史の中で培われてきた人間の絆と地域のコミュニティの息の根に、最後のとどめを刺しかねないものとなっている。
生産と消費と暮らしのあり方を根本から変える
原発がこれほどの脆さと危うさを露呈した今、エネルギー政策は根本から変えなければならなくなった。原発廃絶の年限を明確に定めて、その目標年に向かって、年次ごとに段階的に確実に縮小していかなければならない。同時に、太陽光、太陽熱、風力、地熱、小水力、バイオマスなど、地域に適した小規模かつ再生可能な自然エネルギーを生み出し、それを「地産地消」する分散型のエネルギーシステムへの転換を計っていくことが必要である。
ここで忘れてはならないことは、これまでの生産と消費と暮らしのあり方をそのままにしておいて、それに必要とされるエネルギーや資源(レアメタル・レアアースを含む地下鉱物など)の消費総量の削減を一切問わずに、ただ単にエネルギー源を新エネルギーに転換しさえすればそれで済む、という問題では決してないということだ。人間の欲望のおもむくままに際限なく生産を拡大し、エネルギーと資源の消費量の増大を野放図に放置しておく今日の経済社会の仕組みのままでは、この慢性的エネルギー不足病は解決されない。あまりにも大地からかけ離れた今日の私たち自身の暮らしを省みて、それぞれの家族に農ある暮らしを組み込むことによって、二一世紀にふさわしい新しいライフスタイル(詳しくは、後掲『菜園家族宣言』)を創造し、それを地域社会の基底にしっかりと据えていくことができるかどうか。この転換期にあって、このことが今、問われているのではないだろうか。
こうすることによって、大量生産・大量消費・大量破棄型のこれまでの市場競争至上主義「拡大経済」下の生産と消費と暮らしのあり方は、根本から変えられていくであろう。それは、生産手段(自給に必要な最小限の農地と生産用具など)から引き離され、浮き草同然となった賃金労働者という人間の存在形態を前提とする、一八世紀産業革命以来の社会のあり方からの脱却にほかならない。生産効率が多少下がろうとも、モノが少なくなろうとも、再び家族に自立の基盤を取り戻し、大地に根ざしたより人間らしい、精神性豊かな自然循環型共生の暮らしを築きあげていくことにこそ、希望があるのではないか。文明の分水嶺に差しかかった今、これこそがかけがえのない地球を子孫に手渡す唯一残された道なのではないだろうか。
文明史の一大転換期として、おそらく後世に記憶されるであろうこの東日本大震災に直面し、まさにこの渦中から、私たちはこれまでのものの見方、考え方を支配してきた認識の枠組みを根本から変えるよう迫られている。
昨二〇一〇年五月一日にホームページ上に公開し、その後数次にわたって更新を重ねてきた論考『静かなるレボリューション 菜園家族宣言 ― 人間復活の高度自然社会へ ―』(小貫・伊藤、里山研究庵Nomadホームページ掲載、PDFファイル・A4用紙九二枚分、最終更新日二〇一〇年十二月八日)は、3・11を機に、その意味することをあらためて吟味することになった。この『菜園家族宣言』の中で展開してきた時代認識や21世紀未来社会構想の核心部分は、まさに今、私たちが直面している被災地復興においても、その基本理念、基本原理として生かされなければならない、という思いを強くしている。
(「緊急提言」より抜粋)
『菜園家族宣言』 ― 21世紀未来社会論への試論として
大震災からちょうど三ヵ月後に、福島原発事故を主題に、メモランダム風の小文「あきらめるにもあきらめられない ―東日本大震災から3ヵ月が経って―」(小貫・伊藤、里山研究庵Nomadホームページ、PDFファイル・A4用紙一八枚分、二〇一一年六月十一日)を公表した。
先の「緊急提言」とこの小文「あきらめるにもあきらめられない」のいずれにも、震災前にまとめた前掲の拙論『静かなるレボリューション 菜園家族宣言 ― 人間復活の高度自然社会へ ―』に展開されている21世紀未来社会論としての「菜園家族」構想の基本理念 ―自然循環型共生の思想が、その基底に流れていることに注目していただければ幸いである。
この『菜園家族宣言』は、自然と人間、人間と人間との関係から、二一世紀の人間のあるべき存在形態を根源から問い直し、「家族」や「地域」を新たな視点から捉えつつ、日本の未来のめざすべき姿について全面的に論じた論考であり、21世紀未来社会論への試論となっている。
まず、この『菜園家族宣言』の目次を以下に提示し、その概要紹介にかえたいと思う。
―『菜園家族宣言』の目次 ―
はじめに (1)
1 今日の破局的事態を招いたものは何か (8)
私たちは今、どんな時代に生きているのか (8)
「二つの輪が重なる家族」が消えた (10)
「高度経済成長」以前のわが国の暮らし (12)
「家族」と「地域」衰退の原因とその再生への基本原理 (13)
2 あらためて根源から考える ― 人間とは、「家族」とは何か (16)
「家族」の評価をめぐる歴史的事情 (16)
人間の個体発生の過程に生物進化の壮大なドラマが (18)
母胎の中につくられた絶妙な「自然」 (20)
人間に特有な「家族」誕生の契機 (22)
「家族」がもつ根源的な意義 (26)
人間が人間であるために (29)
3 二一世紀の社会構想 (34)
週休五日制のワークシェアリングによる�「菜園家族�」構想 (35)
世界に類例を見ない ※CFP複合社会 ― 史上はじめての試み (39)
“菜園家族群落”による日本型農業の再建 (43)
森と海を結ぶ流域地域圏の再生 ― 草の根民主主義の土壌 (51)
今こそパラダイムの転換を ― 未踏の思考領域に活路を探る (58)
人間の新たな存在形態が、二一世紀社会のかたちを決める (61)
自然界の原理と二一世紀未来社会 (63)
※ CFP複合社会のCは資本主義セクターC(Capitalism)、Fは家族小経営
(「菜園家族」、「匠商家族」)セクターF(Family)、Pは公共セクターP
(Public)である。
4 いのち輝く「菜園家族」 (68)
ふるさと ― 土の匂い、人の温もり (69)
土が育むもの ― 素朴で強靱にして繊細な心 (80)
5 自然循環の分かちあいの世界へ (84)
『日本列島改造論』の地球版再現は許されない (84)
「菜園家族」の創出は、地球温暖化を食い止める究極の鍵 (89)
低炭素社会へ導く究極のメカニズム ― CSSK方式 (92)
CFP複合社会への移行を促す ※CSSKメカニズム (93)
CSSK特定財源による人間本位の公共的事業 (96)
本物の自然循環型共生社会をめざして (98)
CFP複合社会を経て ※※高度自然社会へ ― 労働を芸術に高める (100)
※ CSSKメカニズムとは、国・都道府県レベルに創設される公的機関�「CO2
削減と菜園家族創出の促進機構」(略称CSSK)と、市町村に設置される
農地とワーク(勤め口)のシェアリングの調整・促進のための公的「土地バ
ンク」との連携によって、地球温暖化対策と次代の社会的基盤となる「菜園
家族」の育成を連動させつつ、解決をはかろうとするメカニズム。
※※ 高度自然社会へ至る人間の存在形態の展開過程は、原始共同体的自由身分
→古代奴隷的身分→中世農奴的身分→近代賃金労働者的身分→高度自然社
会的自由身分(賃金労働者と農夫の融合による二重化された人格としての
「菜園家族」的自由身分)
6 苦難の時代を生きる (105)
今こそ「成長戦略」の呪縛からの脱却を (105)
いまだ具現されない“自由・平等・友愛”の理念 (108)
スモール・イズ・ビューティフル ― 巨大化の道に抗して (112)
7 それでは今、私たちは何からはじめるべきか (122)
一つの具体的「地域」典型から、今何をなすべきかを考える (125)
市町村における地域再生の本当の鍵は、農業・農村問題の解決である (128)
地域社会には、今こそ精密検査による根本的な原因療法がもとめられて
いる (131)
むすびにかえて ― いのちの思想を現実の世界へ (133)
<添付資料>
【提 言】
あらためて戦後六五年の歴史の中で甲良の未来を考える (143)
― 四〇年先の二〇五〇年を見すえて ― (小貫)
(『甲良町新総合計画 二〇一〇〜二〇二〇』― 発行 滋賀県甲良町、
二〇一〇年四月 ― に所収)
★『菜園家族宣言』の全文は、里山研究庵Nomadホームページ
http://www.satoken-nomad.com/ にPDFファイルで公開、A4用紙92枚分。
この拙論『菜園家族宣言』の趣旨を汲み取っていただくために、その一節「6 苦難の時代を生きる」から一部を抜粋し、以下に転載しておきたいと思う。
6 苦難の時代を生きる
今こそ「成長戦略」の呪縛からの脱却を
ここであらためて問題にしたいことは、今日、ここに至ってもなお目先の損得に終始する、近視眼的思考に陥っているこの国の政治的状況である。それをつくり出している原因は、もちろんいろいろ考えられる。しかし、その責任を為政者のみに負わせるのは簡単ではあるが、それでは、本当の意味での解決にはつながらない。むしろ、この国の未来のあるべき姿が見えないところで、絶えず目先の小手先の処方箋のみに終始する議論を強いられ、あるいは、それを許してきた国民サイド、なかんずく自戒を込めて「研究者」の弱さにも、もっと目を向けなければならない。
世界のすべての人々にとって焦眉の課題であり、自己の存在すら根底から否定されかねない地球温暖化の問題は、私たちが生きているこの社会の未来の姿はどうあるべきかを、自分自身の問題として真剣に考える千載一遇の機会として、積極的に受けとめたい。
市場原理に対する免疫力のない脆弱な体質をもった、根なし草同然の現代賃金労働者。こうした人間によって埋め尽くされた旧来型の社会が世界を覆っている限り、同次元での食うか食われるかの力の対決は避けられず、血みどろのたたかいは延々と続くであろう。市場競争は、地球大の規模でますます熾烈さを極め、世界は終わりのない修羅場と化していく。
こうした社会の危機的状況を作り出している根源を不問に付したまま、環境技術による「省エネ」や「新エネルギー」開発に奔走し、装いも新たに未だ「成長戦略」に固執し、その施策を競い合っている姿は、時代錯誤を通り越して、滑稽というほかない。
先にも述べたように、このような時代認識に基づく今日の地球温暖化対策は、一時はうわべを糊塗することができたとしても、決して本質的な解決にはつながらない。それどころか、人類を破滅の道へと誘いかねない。今や世界経済の牽引役と期待されている中国も、これまでの市場競争至上主義「拡大経済」とは同根であり、本質的に何ら変わるものではない。こうした「成長戦略」に乗りにのって勢いづいている中国に、いずれ遠からずやってくるその後の結末と、世界経済への計り知れない連鎖を想像するだけでも、こうした危惧の念を単なる取り越し苦労と、一笑に付すわけにはいかないであろう。
こうした「成長戦略」が広がる中、もはやチェルノブイリ原発の大惨事(一九八六年)は遠い過去のものとなり、忘却の彼方へと追いやられていく。CO2排出量ゼロの「クリーン・エネルギー」を売り物に、原子力発電所は、悪性の癌細胞が増殖と転移を繰り返しながらいのちを蝕むかのように、世界各地に競って建造され、拡散していく。その布石は、もうすでに打たれている。核エネルギーに下支えされた、快適で便利で「豊かな」暮らし。「エコ」とは裏腹に、危険は地球に拡散し、充満していく。このような地球の未来を想像するだに恐ろしい。こんな地球を子どもや孫たちに渡すわけにはいかない。
今こそ私たちは、一八世紀産業革命以来、長きにわたって拘泥してきたものの見方・考え方を支配する認識の枠組みを根本から革新し、新たなパラダイムのもと、これまでとはまったく次元の異なる視点から、社会変革の独自の道を探り、歩みはじめる覚悟と勇気が必要なのではないだろうか。
これは、日本のみならず、世界のすべての人々に負わされた、避けては通れない、二一世紀人類の共通にして最大の課題である。そうでないというのであれば、現状を甘受するほかなく、やがて人類は、熾烈な市場競争の果てに、人間同士のたたかいによって滅びるか、それとも、地球環境の破壊によって亡びるしかないのである。
いまだ具現されない“自由・平等・友愛”の理念
今日の私たちの状況は、残念ながら、人類が自然権の承認から出発し、数世紀にわたって鋭意かちとってきた、一八四八年のフランスにおける二月革命に象徴される自由・平等・友愛の精神からは、はるかに遠いところにまで後退したと言わざるをえない。
不思議なことに、近年、特に為政者サイドからは、「自立と共生」の言葉がとみに使われるようになった。「自立と共生」とは、人類が長きにわたる苦難の歴史の末に到達した、重くて崇高な理念である自由・平等・友愛から導き出される概念であり、その凝縮され、集約された表現であると言ってもいい。それは、人類の崇高な目標であるとともに、突き詰めていけば、そこには「個」と「共生」という二律背反のジレンマが内在していることに気づく。
あらゆる生物がそうであるように、人間は、ひとりでは生きていけない。人間は、できる限り自立しようとそれぞれが努力しながらも、なおも互いに支えあい、助けあい、分かちあい、補いあいながら、いのちをつないでいる。「個」は「個」でありながら、今この片時も、また時間軸を加えても、「個」のみでは存在しえないという冷厳な宿命を、人間は背負わされている。それゆえに、人類の歴史は、個我の自由な発展と、他者との「共生」という、二つの相反する命題を調和させ、同時に解決できるような方途を探り続けてきた歴史であるとも言えるのではないだろうか。
私たち人類は、その歴史の中で、ある時は「個」に重きを置き、またある時はその行き過ぎを補正しようとして「共生」に傾くというように、「個」と「共生」の間を揺れ動いてきた。この「自立と共生」という人類に課せられた難題を、どのような道筋で、どのようにして具現するかを示すことなく、この言葉を呪文のように繰り返しているだけでは、空語を語るに等しいといわれても、致し方ないであろう。
生きる自立の基盤があってはじめて、人間は自立することが可能なのであり、本当の意味での「共生」への条件が備わる。人間を大地から引き離し、人間から生きる自立の基盤を奪い、その上、最低限必要な社会保障をも削って放置しておきながら、その同じ口から「自立と共生」を説くとしたならば、それは、二重にも三重にも自己を偽り、他を欺くことになるのではないだろうか。
ところで、きわめて大切な歴史認識の問題として再確認しておきたいことがある。それは、人間が、イギリス産業革命以来、二百数十年の長きにわたって、農地や生産用具など必要最小限の生産手段さえ奪われ、生きる自立の基盤を失い、ついには、根なし草同然の存在になったという、この冷厳な事実についてである。
一九世紀「社会主義」理論は、生産手段を社会的な規模で共同所有し、それを基盤に共同運営・共同管理することによって、資本主義の矛盾を克服しようとした。しかし、二〇世紀に入ると、その実践過程において、人々を解放するどころか、かえって「個」と自由は抑圧され、「共生」が強制され、独裁強権的な中央集権化の道を辿ることになった。人類の壮大な理想への実験は、結局、挫折に終わった。そして、いまだにその挫折の本当の原因を突き止めることができず、新たなる未来社会論を見出せないまま、人類は今、海図なき時代に生きている。
二一世紀の今もなお、私たちの社会は、大量につくり出された根なし草同然の人間によって、埋め尽くされたままである。大地から引き離され、生きる自立の基盤を失い、根なし草同然の人間が増大すればするほど、当然のことながら、市場原理至上主義の競争は激化し、人々の間に不信と憎悪が助長され、互いに支えあい、分かちあい、助けあう精神、つまり友愛の精神は衰退していく。そしてそれは、個々人間のレベルの問題にとどまらず、社会制度全般にまで波及していく。
生きる自立の基盤を奪われ、本来の「自助」力を発揮できない人間によって埋め尽くされた社会にあって、なおも私たちが「共生」を実現しようとするならば、社会負担はますます増大し、年金、医療、介護、育児、教育、障害者福祉、生活保護などの社会保障制度は財政面から破綻するほかない。それが、日本社会の直面する今日の事態である。
この事態を避けるために考えられる方法は、財政支出の無駄をなくすか、税収を増やす以外にない。しかし、急速に進行する少子高齢化の中で、財政の組み替えや節減、税制改革だけでは、もはやどうにもならないところにまで来ている。「新成長戦略」とか「エコ産業」などという触れ込みで、万が一、「経済のパイ」を大きくし、企業からの税の増収をはかることができたとしても、先にも述べたように、この「拡大経済」路線そのものが、本質的に資源の有限性や地球環境問題と真っ向から対立せざるをえない。しかも、グローバル経済を前提にする限り、「エコ」の名のもとに、市場競争は今までにも増して熾烈を極めていく。「国際競争に生き残るために」という口実のもとに、企業はますます社会的負担を免れようとし、結局、その負担を、庶民への増税として押しつけてくる。
したがって、自立の基盤を奪われ、「自助」力を失い、浮き草のように生きる現代賃金労働者家族を基礎単位に構成される、今日の社会の仕組みをそのままにしておいて、「自立と共生」を語ること自体が、もはや許されない時代になってきていることに気づかなければならない。
「菜園家族」構想は、こうした時代認識に基づいて提起されている。そして、人類共通の崇高な理念であり、目標でもある自由・平等・友愛、つまり「自立と共生」という命題に内在する二律背反のジレンマをいかにして克服し、その理念をいかにして具現することが可能なのか、その方法と道筋を具体的に提起しようとしているのである。
私たちの社会の底知れぬ構造的矛盾に正面から向き合い、大胆にメスを入れ、今日の社会の枠組みを根本から転換することなしに、「自立と共生」を説くとすれば、それは、大多数の国民に、自立の基盤を保障せずに、社会保障をも削減し、自助努力のみを強制するための、単なる口実に終わらざるをえないのは明らかである。
これからどんな政権が新たに登場しようとも、社会のこの根本矛盾、つまり生産手段を奪われ、浮き草のようになった人間の存在形態をそのまま放置しておく限り、ほんものの「自立と共生」の実現への具体的かつ包括的な道は、見出すことはできない。そうした政権は、遅かれ早かれ、いずれ国民から見放されるほかないであろう。
(『菜園家族宣言』より抜粋)
21世紀未来社会論へのアプローチとしての試論的研究は、今から十年前に公刊した『菜園家族レボリューション』現代教養文庫(小貫雅男、社会思想社、二〇七頁、二〇〇一年)をはじめに、続く『森と海を結ぶ菜園家族 ―21世紀の未来社会論―』(小貫雅男・伊藤恵子、人文書院、A5判・四四八頁、二〇〇四年)、『菜園家族物語 ―子どもに伝える未来への夢―』(小貫・伊藤、日本経済評論社、A5判・三七一頁、二〇〇六年)、『菜園家族21 ―分かちあいの世界へ―』(小貫・伊藤、コモンズ、四六判・二五六頁、二〇〇八年) を経て、今日に至っている。
正確には、『菜園家族レボリューション』の一年前に自家版として出版した小冊子『21世紀・日本のグランドデザイン― 週休五日制による三世代 菜園家族酔夢譚』(小貫、Nomad、B5判・九〇頁、二〇〇〇年)からはじまるのであるが、この小冊子は、なぜか沖縄・八重山群島の竹富島にある喜宝院蒐集館に平積みされていた。ちょうどその頃に、自然と人間の本源的関係を見直し、二一世紀にふさわしい価値に基づく新しい経済学のあり方を探究しておられた藤岡惇さん(立命館大学経済学部教授)が、ゆるがぬ平和の礎となる「うつぐみ(協同)の精神」をもとめてここを訪れていた折に目に留め、以来今日まで、「菜園家族」構想を支えて下さることになった。曰く因縁付きの、あらゆる意味で記念すべき小冊子である。この十年間の世界の激変を経て、今あらためて読み返してみても、そこには、「菜園家族」構想の骨子を成す重要なエッセンスが詰まっており、この「構想」の原形として今なおその意義を失うことなくとどめているものと思っている。
『菜園家族レボリューション』については、森岡孝二さん(関西大学経済学部教授)から、『働きすぎの時代』(岩波新書、二〇〇五年)の中で、「菜園家族」構想の核心部分とも言えるCFP複合社会に着目された論評をいただいた。この論評は、六年前のものとはいえ、この「構想」成立までの事情といい、的確な要約といい、実に正鵠を得ている。働きすぎの問題や地域社会の衰退がいよいよ深刻になっている今、そこでの氏の指摘の重要性は、ますます大きくなってきている。少し長くなるが、この論評から一部を以下に引用し、「菜園家族」構想の要約紹介にかえさせていただきたい。
(以下、森岡孝二『働きすぎの時代』第五章より抜粋)
小貫氏は一九七〇年以来たびたびモンゴルを訪れ、遊牧民の地域社会に分け入り、一九九二年の秋からは山岳と砂漠の村ツェルゲルで一年間の住み込み調査を行った。ドキュメンタリー
『四季・遊牧 ―ツェルゲルの人々―』はそのときの記録である。(中略)それと同時に、「際限なく拡大していく欲望と消費と生産の悪循環」のなかで日本の地域や社会が抱える問題点を、モ
ンゴルを見つめる視点から問い直し、「菜園家族レボリューション」の構想を打ち出し広めてきた。
この構想が描く菜園家族社会は、資本主義セクターC(CapitalismのC)と、小経営家族セクターF(FamilyのF)と、公共セクターP(PublicのP)の三つのセクターから成る「CFPの複合社会」である。この社会は週休五日制であって、人々はCセクターからPセクターで週二日働き、従来型の工業その他の産業に従事するか、行政・教育・医療・社会福祉などの公務労働を担う。他の五日はFセクターの菜園で農業を営むか、自営の形で商業やサービス業や手工業に携わる。
週休五日制といいながらその五日も働くという点では働いてばかりという感じもする。しかし、週二日のC・Pセクターでの仕事によって給与所得を得るうえに、Fセクターである程度まで自給自足できることによって、安定した生活基盤がある。しかも、商品作物を作り、農業以外の仕事にも従事してもっぱら貨幣収入を追求してきた従来のいわゆる兼業農家とは違って、菜園家族は市場依存度が低く、消費に対する欲求も適度に抑制されている。そのために、人びとは過重な労働から解放され、時間的なゆとりを手に入れて、自由で創造的な活動により多くの時間を振り向けることができると考えられている。
農業にいそしむ小経営家族を軸とした社会改造プランは、小経営を抑圧した従来の社会主義とは根本的に異なる。このような構想を実現するには、土地利用の問題をはじめとしてさまざまな困難があると予想される。とはいえ、これまでの大量生産・大量浪費の「拡大系の社会」から、人間と自然の物質代謝を持続可能にする「循環系の社会」に移行する必要があるとするならば、菜園家族社会の構想は十分に検討するに値する。一方に大量の失業者が存在し、他方に大量の長時間労働者が存在するような不合理を解消するには、ライフスタイルと社会システムの転換を同時に可能にするワーク・シェアリング(仕事の分かち合い)が求められるが、それを意識的に組み入れているのが菜園家族社会の構想である。衰退した農業や林業を復活させ、地域の固有性や生活文化や職人芸を蘇らせるためにも、この構想に学んで、市場原理の暴走を自然に制御する仕組みを社会のなかに埋め込む必要がある。
(以上、森岡孝二『働きすぎの時代』第五章より抜粋)
また、編集者であり作家でもあり、今でもふるさと信州・上田にて精力的に執筆活動を続けておられる九五歳の大先輩、小宮山量平さん(理論社創業者)は、『森と海を結ぶ菜園家族 ―21世紀の未来社会論―』以来今日まで、幾度となく熱い思いを込めて論評※ して下さった。資本主義の矛盾を生産手段の社会的規模での共同所有とそれを基盤とする共同運営・共同管理によって、上から強権的に克服しようとしたA型発展の道(ソ連型社会主義)への批判として対置したのが、B型発展の道である。このB型発展の道とは、生産手段(自給に必要な最小限の農地と生産用具と家屋など)と現代賃金労働者との再結合を果たすことによって、二重化された人格をもつ「菜園家族」という新しい人間の存在形態を創出し、これを基調とするCFP複合社会をめざす社会変革の道筋であるが、小宮山さんはこれに注目され、そこに大地に生きる人間復活の可能性とその今日的意義を認め、論じられたのである。戦前、戦後の動乱期、そして現代の混迷に至るまで、日本社会の来し方行く末を、歴史的実体験に基づく深い洞察と広い視野から、一貫して見据えてこられた方からの論評だけに、なおさら励まされるところが大きかった。
こうした多くの人々に支えられ、十余年にわたりこの「菜園家族」構想の深化をめざし、調査と研究に取り組んできたが、それでもこの「構想」の意図や全体的な内容は、今日、時代が求めている未来社会論の革新と深化という課題要請からすれば、残念ながら一般の読者や研究者にまだまだ十分に伝わっておらず、活発な議論も広がっていないというのが実情であると言わざるをえない。それは、ある評者が言うように、この「構想」があまりにも時代の「常識」からかけ離れているためなのか�・�・�・とも訝るが、今、3・11を境に時代は激変し、人々の意識も大きく変わろうとしている。こうした客観的世界の深部からの大きな変化の兆しを信じ、対話を通じて多くの人々の意見に耳を傾け、「構想」のさらなる深化にじっくりと取り組んでいきたいと思っている。
先に紹介した「緊急提言」、小文「あきらめるにもあきらめられない」、論考『菜園家族宣言』は、いずれも里山研究庵Nomadのホームページから気軽にPDFファイルをダウンロードしていただけるものになっている。これらと合わせて、ぜひ先に挙げた公刊書もお読みいただければ幸いである。
※『森と海を結ぶ菜園家族』について小宮山量平さんが書かれた論評の全文を
本稿の末尾に掲載した。
まとめにかえて ― 対話を通じて希望の道を拓く
大震災から半年。復旧・復興をめぐって国や県、財界などの上からの構想案が次々と出揃いつつある。効率化、集約化、「職住分離」などといった考えのみが先行するこれらについて徹底的に吟味し、対抗軸となりうる未来への確かな展望をいよいよ打ち出さなければならない時に来ている。そのためには、具体的な現実世界に向き合って、地道な調査・研究と学習運動の力強いネットワークを地域から広げていくほかないのだと、日々痛感しているところである。
ややもすると、これまでの価値観から一歩も抜け出すことができずに、目先の処方箋や、短絡的できわめて技術的な個々の細部の議論に終始しがちな傾向の中にあって、地域や労働の現場に生きる人々の立場に立った、かつ二一世紀日本のめざすべき方向をも見据えた総合的で全一体的な研究と、それに基づく未来へのより具体的な道筋の提起が、今ほど必要な時はない。このことは、このたびの大震災からの復旧・復興のわずか半年の中での混迷・混乱という国民的体験からも言えることではないだろうか。
私たち自身、東北の風土やなりわい、歴史的変遷と現状など、地域の具体的な様子を知り、さらに学んでいきたいと思うと同時に、特に二一世紀日本社会のあり方については、これからも時間をかけて、長い目で考えていかなければならないと思っているところである。
3・11を機に、政府や財界や大手シンクタンク、コンサルタントなど各方面から出されている復興計画に対して、科学的に批判し、かつ批判にとどまることなく、さらにその対抗軸となりうる有効で包括的な未来への展望と具体的な対案を提示していくためには、それを導きうる理論的大前提となるべき21世紀未来社会論の探究と深化が、わが国においては欧米諸国に比べ、平時の普段からあまりにも不活発で不十分であったと言わざるをえない。それゆえにこれからは、自然、社会、人文科学のあらゆる研究分野の導きの指針となる「生命本位史観」ともいうべき二一世紀の新しい歴史観が、特に3・11以後の今日の時代状況に応えうるものにまで深められ、高められなければならないと痛切に感じている。
特に時代の大転換期においてはなおのこと、理論の再構築は、具体的現実から出発し、抽象へと向かわなければならない。抽象のレベルから抽象へと渡りながら、抽象レベルでの概念操作 ― 概念間の連関性や整合性の検証に終始し、それを延々と繰り返すだけでは、新たな時代に応えうるパラダイムの転換も理論も生まれるはずがない。
今こそ具体的現実に立ち返り、そこから再出発し、何よりもまず二一世紀の新たな歴史観の探究と構築に努め、それを導きの糸に、「地域研究」、経済学研究への新たな着手に取り組み、一からはじめるぐらいの心づもりで、これまでの未来社会論を根源から問い直さなければならない。分野の垣根を乗り越え、自由闊達な対話と真摯な議論を通じて、わが国の現実に立脚した、まさに草の根の21世紀未来社会論を再構築していくことが急務なのではないか。
論壇やマスメディアにおいては、大震災前の旧態依然たる価値に基づく「新成長戦略」の論調が、半年も経たないうちに早くも復活し、横行している。これも一つには、私たち自身の草の根の21世紀未来社会論の不在に遠因があると言わざるをえない。こうした憂うべき現状を、広範な国民的対話と議論を通じて、何としてでも克服していかなければならない。
長くなってしまった。大震災からの復旧・復興を考えるに際しても、さらには、今日もっとも急を要する21世紀未来社会論の構築・深化のためにも、先に挙げた小文や拙著が、ささやかではあるが初動の一つのたたき台として、対話と議論のきっかけになればと願って、大震災から半年が経った今、解説を加えあらためて提示した次第である。
2011年9月18日
琵琶湖畔、鈴鹿山中大君ヶ畑にて
小貫雅男
伊藤恵子
 里山研究庵Nomad 里山研究庵Nomad
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑452番地
TEL&FAX:0749−47−1920
E-mail:onuki@satoken-nomad.com
http://www.satoken-nomad.com/
★ 追記:『森と海を結ぶ菜園家族 ―21世紀の未来社会論―』(小貫・伊藤、人文書
院、2004年)について、月刊誌『自然と人間』に二回にわたって掲載された小宮山
量平さんの論評は、今から六年前の2005年に書かれたものであるが、3・11後のま
さに今読み返してみると、その指摘の的確さとその重さをあらためて思い知らされ
るのである。初心に立ち返るつもりで、以下に全文を転載した次第である。
21世紀の未来社会論
― 今こそほんとうの学習運動の燃え上がる季節が訪れている ―
小宮山量平(理論社創業者・作家)
あのヒトラーによるファシズムの波が押しよせていたころ、独仏国境にほど近いストラスブール大学の若者たちを励ますかのように謳われたアラゴンの長い詩の中に、とりわけ心に残る一節がありました。
教えるとは希望を語ること
学ぶとは誠実を胸に刻むこと
戦後日本の焼け野原へと帰ってきた若者たちも、こんな一節をつぶやきながら祖国の明日を見つめたものです。今私が机上に開いている一冊の本の冒頭には、ちょうどあのころの敗戦の国土を彷彿とさせるような文章が数多くあって、きりきりと胸が痛みます。
「人々は欲望のおもむくままに功利を貪り、競い、争い、果てには心を傷つけあい、人を殺し、国家も『正義』の名において、多くのいのちを殺すのです。�・�・�・これほど大がかりに、しかも構造的に人間の尊厳が傷つけられた時代も、ほかになかったのではないでしょうか。」
この本は昨年(二〇〇四年)の十月に刊行された一冊なのですが、あたかもあの敗戦直後の祖国を眼のあたりにしているかのような嘆きを覚えるのです。
なるほど、人によっては第二の敗戦の訪れではなかろうか、と、嘆きを深めないではいられないほどの社会現象が相次いで生じています。とりわけ今ほど人間の労働が軽んじられたことはありません。
「今流行のパート、フリーター、派遣労働者。そのどれ一つとっても、これでは使い捨て自由、取り替え自由の機械部品同然ではないでしょうか。これほど人間を侮辱し貶めたものもないのです」と、指摘した著者は、あらためて「現代賃金労働者」の問題を根源的にとらえなおそうと迫っています。
私にこの分厚い一冊を送って下さったのは滋賀県立大学人間文化学部の教授・小貫雅男氏で、そのタイトルは『森と海を結ぶ菜園家族』とあり、「21世紀の未来社会論」と副題が添えられ、若き同学の伊藤恵子さんとの共著となっております。お互いにいまだお会いしたこともない私にこのような労作を贈って下さったのは、「『自然と人間』の巻頭言を読ませていただいています」と言うことで、それだけで私には名状し難い同志感が湧いたものです。けれども持ち重りのするこの一冊のページをめくりながら、ちょうど今二〇〇ページ余第四章まで読み進んだ時点で、もはや充分に私の胸は熱くなるのでした。
ああ、こういう本こそが待たれていたのだ!※ ―― と私はつぶやかずにはいられませんでした。ちょうどアコヤ貝がその胎内に異物を容れられる、さぞかし痛みもし不快であろう、排除しようと全身でもだえ、体液を分泌して、その異物を包み込む―と、いつしかその異物を溶かし込んで、円やかな乳色の結晶が�・�・�・と、あの美しい真珠の誕生を勝手に空想しながら、私は、今の世の苦しみとの格闘の中から、格別に美しい珠玉の生まれ出ることを期待し、今こそそんな新生の時代が到来すると、待望していたのでした。
まぎれもなくこの一冊は「21世紀の未来社会論」として、こんなにも労働が貶められ、こんなにも正当な権利が踏みにじられ、こんなにも希望の着地点から遠ざけられている若い同胞たちのために、当代の悩みと苦しみという「異物」との格闘の中から生まれて来たと思うのです。希わくはこの一冊を三分冊ほどのハンディなテキスト判として、各地で希望を語り、誠実を胸に刻む学習の環が生まれたらと夢見るのです。
※ あたかも私たちの世代が青年だったころに河上肇先生の第一第二『貧乏物語』
にめぐりあった時に感じたようなやさしさと説得力に富んだ本の出現です。
(月刊『自然と人間』2005年1月号 連載巻頭エッセイ「千曲川のほとりで」第27回
より転載、発行 自然と人間社)
生命再生産の認識論
― いのちを見つめながら考える新学習運動展開のすすめ ―
小宮山量平(理論社創業者・作家)
ありがたいことに米寿を越えたこの老骨を囲んで、フレッシュな学生諸君たちのゼミを企ててくれた大学がありました。一橋大学の就職世話係の先生が、私のような変り種の先輩の話も聞いてみては、と、有志の若者たちに声をかけたのでしょう。男子四名(うち一名は中国人留学生)と女子二名の六名が、東京の私のアトリエに所狭しと集まったのです。以下問答体ふうにその骨子をまとめて紹介したいと思うのです。
小宮山 みなさんを見ていると、まるで私の孫のようで、今やずいぶん酷い時代に世に巣立って行かれるものだ、と、心が痛むのです。ふつう卒業しての首途であれば、前途洋々の着地を祝い、オメデトウと眼を細めたいところです。けれど二一世紀の初頭に入ってから、そういう喜びが急速に失われつつあるのは、どうしたことなのでしょうか?
学生A 確かに私たちの周辺でもメデタイ気分は少なく、できれば留年でもして、もう少し勉強していたいような気分が大いにあります。
小宮山 それというのも諸君を迎える「未来社会」がきわめて不透明で、私どもが「キャプテン・オブ・インダストリー」などと励まされて卒業したような空気は全くない。どんな企業を選んでみたところで、生涯の夢を託するほどの安定性は望めません。この『自然と人間』誌新年号の「21世紀の未来社会論」が語るように、今や人間の労働が極端に軽んじられ、人間の誇りがこんなに貶められている時代はありません。なぜこんな時代を迎えることとなったのかが解明されているはずです。ではどうしたらこの状態から脱出できるのか。この本の著者(小貫雅男教授)たちは、従来の社会変革論の諸説をたどって、その多くをA型発展の道を目指して挫折したものと分類した上で、今こそ大胆にB型発展の道※ を目指すべし、と、提唱するのです。
学生B 確かにソ連や中国における社会主義的な実験が、二〇世紀末に崩壊した現実のショックは、ぼくら世代にも一種のトラウマとして残って、新しい提案には懐疑的です。
小宮山 そうした傷痕を舐めるようにして、世界各国のニューレフトによる反省や批判や修復が試みられているのも事実です。しかし思い切って、敢えて根源的にB型発展の道への探究に踏み切った点で、小貫教授たちによる「森と海を結ぶ菜園国家」の構想は、こんなにも人間の労働が貶められている時代に巣立とうとしている諸君の心に、希望の灯をともすに違いないと思うのです。
学生A そうしたテキストが生まれたことは注目すべきことで、ぼくらもこの本に挑戦してみましょう。
小宮山 そう、その上でもう一度このゼミをやってみましょう。今日は、そんな勉強への弾みとなるようなヒントだけを指摘しておきます。
実はこの正月、日本の主要新聞の多くが挙って少子化問題を最大の危機現象として特集しております。そうした認識の土台には、近未来における国家的な生産力低下への危惧があり、各紙とも社会政策的な知能をしぼっているかに見えます。
けれども今こそ「労働力」は単なる商品ではなく、従来の資本や経営の概念で、その値打ちを左右しうるものではないことを、認識すべき時が訪れている、と、肝銘すべきです。労働力を生命力と置き換えた上で、その「再生産」がどのように祝福されるものとなるのであろうか ―― 小貫教授グループの「菜園家族」という構想には、生命の復活へと私たちの認識を導く光明が潜んでいます。
※ ロバート・オーウェン型空想社会主義者からレーニン、スターリン、毛沢東な
ど現実的革命家すべてが提唱した資本主義から社会主義を経て共産主義へとい
たる「A型社会観・発展観」に対する、オルタナティブな「発展」観を指す。
(月刊『自然と人間』2005年3月号 連載巻頭エッセイ「千曲川のほとりで」第29回
より転載)
※ 下記の文書と本をあわせてご一読いただければ幸いです。
◎印は、当方のホームページに公開中。まずは気軽にお読み下さい。
◇印は、公刊された本。さらに内容を深めたい方は、時間をかけてお読み下さい。
◎ メモランダム風小文「あきらめるにもあきらめられない ― 東日本大震災から3ヵ月が経って ―」(小貫・伊藤、里山研究庵Nomadホームページ掲載、PDFファイル、A4用紙18枚分、2011年6月11日)
◎ 緊急提言「東日本大震災から希望の明日へ ― 大地に生きる人間復活の道は開かれている ―」(小貫・伊藤、里山研究庵Nomadホームページ掲載、PDFファイル、A4用紙23枚分、2011年4月26日)
◎「菜園家族宣言 ― 静かなるレボリューション ―」(小貫・伊藤、里山研究庵Nomadホームページ掲載、PDFファイル、A4用紙92枚分、2010年12月8日更新)
◇『菜園家族レボリューション』現代教養文庫(小貫、社会思想社、207頁、2001年)
◇『森と海を結ぶ菜園家族 ― 21世紀の未来社会論 ―』(小貫・伊藤、人文書院、A5判・448頁、2004年)
◇『菜園家族物語 ― 子どもに伝える未来への夢 ―』(小貫・伊藤、日本経済評論社、A5判・371頁、2006年)
◇『菜園家族21 ― 分かちあいの世界へ ―』(小貫・伊藤、コモンズ、四六判・256頁、2008年)
◇ ブックレット『森と湖(うみ)を結ぶ 菜園家族 山の学校』(小貫・伊藤、里山研究庵Nomad、A5判・114頁、2009年)
Copyright (C) Nomad,All Rights Reserved.
|