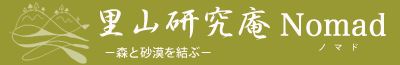
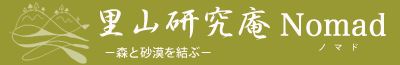 |
| ::::ホーム::::掲示板::::メール::::リンク:::: |
|
メッセージ・感想
|
|
|
|
| メニュー |
| 制作現場からのメッセージ |
| 試写室からin大阪 |
| 湖畔の教室から |
| △TOP |
監督・撮影 小貫 雅男
このパンフレットの冒頭の「解説」を書きながらはじめて気づいたことなのであるが、この作品に対する自分の位置が、微妙に揺れ動いているということである。あるときは、作品をすでに自分の手から離れた、客観的な存在として見ることのできる位置に立ちながら、あるときは、この作品がまだ自分自身の分身のように思えて、作品自体を、冷静に見ることができない位置に立たされている、といった具合に、意識は両者の位置を揺れ動いている。
よく考えてみると、このようなことは、制作の過程でも絶えずおこり、苦しめられてきた。編集上ちょっとでもうまくいったときなどは、有頂天になり“自己陶酔”して、翌日、冷静さを取り戻したときには、奈落の底に突き落とされたような消沈と“自己嫌悪”に苛まれることしばしばであった。編集の5年間というものは、こうしたことの繰り返しであった。その間に、第三次にわたる試作品をつくり直しながら、何とか螺旋状に少しは上向きに登ってきたのかもしれない。
一般にこうしたことは、“表現”というものの本質からくる避けがたいことなのかもしれないが、このような繰り返しの鍛錬をぬきにしては、“表現”は成立しえないのかもしれない。
先の「解説」を書いた時点は、この作品ができあがった直後でもあり、事を成したときによくある満足感にひたれたときで、少し“ハイ”の状態にあったのかもしれない。「解説」の文中には、「美事に描いている」などと立場を混同させ、筆の勢いでぬけぬけと自己賞賛した個所などもあるが、それはそのときの素直な真情の吐露として、そのままにとどめておくことにして、あえて書き変えることはしなかった。
制作中の束の間の自己満足による“自己陶酔”も、全く許されないとすれば、おそらく本来主観性に多くを依拠せざるをえない“表現”という不安定な人間的営為は、少なくとも私の場合は、頓挫していたにちがいない。
今から考えて見れば、この“自己陶酔”なるものは、“表現”の次のよりましな水準に向かうための、一面では大切な目標設定の意味あいを果たしていたのであり、その直後にくる“自己嫌悪”によってはじめて、“表現”の内実の実質化がはじまるのである。“自己陶酔”と“自己嫌悪”の繰り返しによって、私の場合、次のよりましな “表現”への実質化がおこなわれてきたような気がする。映像作品の制作は、今回がはじめてであったので、こんなことをとくに強く痛感したのかもしれない。
NHKの冨沢満さんとプロダクション大日の久島恒知さんは、監修者としてこの制作のはじめから終わりまで、実に忍耐強く見守ってくださった。お二人は今から思うと、どちらかといえば“自己陶酔”の方へ絶えず私を引きあげてくださったように思う。“自己嫌悪”へ追いやるなど、とんでもないと思われたにちがいない。それほど私の自信のなさが、お二人には深刻に映ったのかもしれない。つまりは、おだてて挫折から予防してくださったのである。この作品は、おおくの方からのこのような支えがなかったなら、おそらく完成に漕ぎ着けることはなかったと思う。とにかく、こんな形で作品ができあがったこと自体、自分でも不思議に思っている。今から思うと無謀というほかない。
肉眼で見る世界と、カメラのレンズで切りとった映像の一つ一つのカットを積み重ねてつくりあげてゆく世界との間には、大きな隔たりがある。もちろんそれは客観的世界のコピーなどというものでは決してない。それは、客観的世界をカメラのレンズによって切りとった映像の一つ一つのカットをつなぎ、積み重ねていくことによって、制作者の意識の中にすでに構築されていた世界を再構成し、描き出す独自の世界なのである。この世界は、もはや客観的世界とは同一のものではなくなっている。今回、一般に“表現”とはこのようなものではないかと、身をもって実感した。
この作品がどんな作品になっているのかは、今はわからない。しかし、この作品の最大の特徴はといえば、フィールドで極めて長期にわたって時間をかけ、ようやく結ばれてきた意識の中の像を、これもまた、長期にわたって時間をかけて、現実世界から切りとった映像の一つ一つを丹念につなぎ、練り上げてきた、という点にある。この作品について、今私に間違いなく言えることは、このことだけである。
“自己陶酔”と“自己嫌悪”のはざまで揺れ動く不安は、制作が終わった今も変わらない。その繰り返しの6年間、厳密にいえば9年間の“悪循環”の円環を、この作品が自らの力によって、どこかで断ち切ってくれることを切に願うのみである。
カメラをまわしている時も、制作中もいつも考えていたことがある。この広い地球の一角のそのまた遠隔の片隅で、実にひたむきに、つつましく日々生きている人々がいるという、この冷厳な事実である。そして、その事実の重みについてである。そこでは、贅沢三昧に暮らしている我々先進諸国といわれる地域の人間には想像もできない世界がありながら、不安や悩みや喜びや悲しみなど、お互いの心のひだにまで分け入り触れ合うとき、意外に共通性がおおいことに気がつく。宿命としかいいようのない“いのち”というものを背負った人間の心の底に、深く響きあう哀切といったものを感知したとき、しだいに人間としての連帯感が蘇ってくることに気づくのである。撮影のときも、制作のときも、私はこのことを出発にしなければならない、と思いつづけてきた。
編集 伊藤 恵子
編集というものは、普通、現場に入らなかった人がやるものらしい。その土地・分野に関する特別の予備知識なく、初めて見る人の立場に立って、分かりやすく組み立てることができるから、ということであるようだ。
しかし、この作品に関しては、編集者自身にとって初めてのモンゴルでの一年、初めての編集。思い入れもひとしおである。作品に対する監督の意図をくみ取り、構築したい全体像をつくり上げるために、1つ1つのカットを選び、組み立ててゆこうと努力するのだが、120時間にもおよぶ素材テープをあらためて見ているうちに、ツェルゲル村の一人一人の遊牧民たちへの愛着がよみがえり、時には本流からそれた細部のおもしろさへと、執着してゆくきらいもなきにしもあらずであった。
こうした細部が結果として、作品全体を生かすのか、それとも流れをよどませ、伝えようとすることを見えにくくしてしまうのか、その判断は編集が1次、2次、3次と進行してゆくうちに、あたたかいアドヴァイスのおかげもあり、ある程度までは整理されていったつもりである。
そして究極において、制作過程のさまざまな困難、迷い、不安から目を覚まさせ、この作品の創作の原点に立ち戻らせてくれたのは、いつも、ツェルゲルの人たちが夕暮れのゲルの中、あるいは晩秋の高原で、しんみりと語ってくれた、「この大地に生まれ、生き、この大地に還ってゆくんだよ。」という一言であった。
今、日本では、都市にせよ、農村にせよ、人間が仲間とともに生き生きと暮らし、未来を託す次世代を育む空間「地域」のあり方が、大きく問われている。命をつなげる基本である食べ物さえ、極端にいえば、素材の実体を見ることもなく、加工済みの出来合いばかりで済ますことさえ可能な時代、「土」や「命」の実感・感触を知らずに育ち、生きている人も多い。
一方、この作品の舞台のツェルゲル村の遊牧民たちは、どうであろう。「命」の源の水、土、太陽。そして、草や家畜たち。絶えず我が身を直接、厳しくも豊かなモンゴルの大自然にさらし、生きている。子供たちがお母さんやおばさんに混じって一生懸命、乳搾りを覚えたり、わずかに湧き出る泉から馬と分け合って、夕餉の支度に使う水を汲んだり、砂漠で野生のニラを摘みあつめたりするのも、これから、このツェルゲルという空間「地域」にとけ込み、根づいてゆくための大切な準備なのである。しかも、子供たちは、それを“仕事”として、というより、ゆったりとした毎日の時間の流れの中で、のびのびとした“高度な遊び”という感覚で、身につけていっているように感じられる。
むろん、この辺鄙な内陸アジア奥深い、砂漠・山岳の村とて、完全に外界から遮断され成り立つことのできる桃源郷ではない。とくに“社会主義”体制のたががはずれた近年は、世界を覆い尽くさんばかりの市場経済の波が容赦なく押し寄せており、「地域」のあり方が、これまでになく根本的な変化を余儀なくされることは、まぬがれえない現実となっている。遊牧地域にも、商人たちの手によって、目移りするような多種多様な外国製品が持ち込まれるし、遊牧民たち自身も、畜産物の有利な直販のために首都に赴き、そこで展開している物質生活および社会の急激な変化を目の当たりにする。
このような中で、これから遊牧民たちの暮らしの空間「地域」は、どのような道を歩んでゆくのだろうか。便利さの追求を否定することはおこがましいが、それと引き換えに、自然と人間の間に、長い時間をかけてつくられ、継承されてきたかかわり・対話が、失われていってしまうのだろうか、とも思えてくる。例えば、裸山にわずかに生える灌木の枝に触れ、その枯れ具合を一本一本確かめる遊牧民の奥さんのまなざしには、もうそろそろ燃料に使わせてもらってもよいでしょうか、という問いかけと、確認がこもっているように見えてくるのである。
ともあれ、ツェルゲルの人々は、長い長い歴史の中で、ふるさとの大地の厳しさも恵みも知り尽くしている。遊牧が大地から離れては成り立ちえないものである限り、きっとツェルゲルの人々は、その大地に依拠したツェルゲルらしい暮らしの空間を築く方向で、今後も模索をやめることはないであろう。
その姿に、我々、とくに「命のうすくなった」といわれ、時に行き先の見えなくなっている若者も、大きな力を得、学ぶことが多いのではないかと思う。
この作品には、もちろん英雄も登場しなければ、主人公さえいるようでいない。みんな普段着の遊牧民たち、もっと言えば、隣近所にいる普通のおばさん、おじさん、お転婆っ娘にやんちゃ坊主、といった人々である。そして、この作品を制作したのも、特別そのための高度な修行をしてきたわけでもない素人である。終始温かく見守り、ご助言を下さったり、技術指導をして下さったりした方々も、プロの立場でというより、「地球に生きる一市民」のお心根で、6年の長い制作を支えつづけて下さったのだと思う。若輩の私が参加させていただいてきた調査活動自体、多くの方々のご努力によっておこされ、成り立ってきたことである。
このように、直接、間接に、数え切れない多くの皆さんの支えがあって、できあがったこの作品も、6年の長い過程の末、ついに人前に出てゆくことになった。普通の人々を描き、普通の人々の力で作り上げたこの作品を、今度は鑑賞にあたっても、普段着の皆さんと触れ合い、分かち合ってゆくことができたら、と思う。そんなつながりが少しでも広がれば、あの大地で懸命に生きている、ある意味ではこの作品の共同制作者でもあるあのツェルゲルの人たちが、我々に与えてくれた力を、たとえそれが巡り巡って間接的にでもいい、少しでも返してゆくことになるのではないか。そうしてはじめて、この作品自身にも少しずつ「命」が吹き込まれるのだろう。
制作を終えた今、自分なりにそんな意義を見いだしているところである。
| △TOP |
吉本 周平 (41歳)
大阪府立住吉高校教諭
最近、テレビで「モンゴル」をよく見かける。美しい草原、ナーダムにホーミー、篤い人情と友情。過酷な自然、混乱と貧困、山火事そしてマンホールチルドレン。好奇心や取材の「対象」、ドラマや感傷旅行の「舞台」としての「モンゴル」。現地での取材、映像には嘘はないはずだとは思っても、イライラがつのる。そこには「モンゴル」という自然だけがあり、「モンゴル人」という人々しかいない。地名も人名も「モンゴル」以外はまるで必要ないかのようだ。
しかし、この映像はまったく違う。固有名詞こそ大切な世界だ。ツェルゲルの大地。その自然と不即不離の日常生活を営み、互いに手をつなぎつつ何とか現代を生き抜こうとしているツェンゲルや“没落貴族”アディアスレンたちがいる。その生活をまるごと記憶に刻み込み、心と身体を育んでいく“御曹司”セッドや“次女”ハンドのような子供たちがいる。生身のツェルゲルの人たちが、見る者の中に住まい始める。同時代を生きるツェルゲルの人たちが心の中に住まうようになる。
私にも家庭があり、生活があり、日本の一都市で同時代を生きる。何を大切にし、誰と手をつないで生きていくのか。息子達は、心と身体に何を刻み込んで育っていくのか。ツェンゲルが、アディアスレンが問いかけてくるのである。
三秋 尚 (72歳)
宮崎大学農学部 名誉教授
地球が悲鳴を上げている。それは資源とエネルギーの大量消費のもとで、便利さや物質的豊かさを追い求めてきた“ひずみ”のせいである。人びとは今、地球防衛のため「自然との共生」、「環境調和」、「心の豊かさ」などのキイワードを大合唱している。
ところで約3千年来、アジアの深奥部でこれらのキイワードを実践・継承している草原の民がいる。それは現在のモンゴル国の遊牧民である。遊牧とは、人間の「家畜と共に自然の一部として生かされる営み」であり、その実情を映像が伝えてくれる。
上映中、ツェルゲルでの一年間の足跡を、映し出される画像に誘われて、思い出した。臨場感あふれる内容で、人々の暮らしが隅々まで描かれている。テレビの紀行番組などで放映されるモンゴル遊牧民の暮らしは、言ってみれば、一つときの表面的なもの。彼らの感情や生活のにおいがあまり伝わってこない。四季のうつろいの中で、それぞれの季節感が引きたてられ、季節のくらしの特色がうかがえる。
私たちは、本作品に登場する同国ゴビ山岳部の人びとから、地球に優しい暮らし方の原点を学ぶことができるにちがいない。
村井 宗行 (50歳)
モンゴル近現代史研究家
モンゴル研究を専門とする立場からこの作品を見れば、モンゴル西南部の四季の生活基本形態であるところの、ひいては、社会的・精神的生活であるところの遊牧生活を、映像を通じて記録しているのは貴重であり、いまだかってなかった、と私は思う。とりわけ、ホルショー(遊牧民協同組合)の結成、乳製品製造過程遊牧形態(冬営地から夏営地への移動)、ホト・アイル(複合家族)、サーハルト(村落)、ゲル(モンゴル型家屋)などの映像記録は、学術的価値がある。
それはさておき、映像作品としてみた場合、主要な登場人物であるツェンゲル一家と、それを取り巻く人々をとおして、家族というものがどういうものであるべきかを訴えている、と私はみた。その手法は、時には推理小説的であり、ときにはコメディー・タッチであったりするが、それぞれの人物の個性が描き分けられているのが目をひく。楽天的な女性(母親)、おとなへの少しばかりの背伸びをする微笑を誘う少女、ナイーブで純粋な男の子、貧しくとも充実した精神生活を送る親友。こうした人々がよりよい生活を目指して協同して働く姿は、感動的である。
そして、特に印象に残った言葉は、「大臣も遊牧民も死んだら同じ」というこの作品の中心人物の独白だった。実にそのとおりだと思う。
榊 正明 (51歳)
日本ユーラシア協会 大阪府連事務局長
一瞬のうちに多くのものを破壊した阪神大震災。人々は、夥しい瓦礫を前に都市が「砂上の楼閣」であることを体感した。そして、地域住民の助け合いや全国のボランティア達の活動に、「人の心のあたたかさ」を知って涙した。
20世紀も間もなく終わろうとする今、都市と農山漁村とのあるべき関係についての真剣な探求と実践が求められている。そのことなしに、人間社会のまっとうな発展は、望むべくもない。少なからぬ人々が、そのことに気づき始めている。そして、心ある人々が、困難ではあるが、価値あるこの仕事への模索を始めている。道のりは遠いが、進むべき確かな一筋の道に違いない。
「四季・遊牧」の中で紹介されているツェルゲルの人々の日々の営みも、そのような共同の模索のひとつなのかもしれない。そう思えた時、かの地の人々への形容しがたい愛しさがこみあげてくる。
阿部 治平 (59歳)
埼玉県立伊奈学園総合高校教諭
今まで見たヴィデオで遊牧地帯というと、何となくロマンチックで、のんびりしていて、日本社会から見たらよほどいいところに思える。澄みきって黒く感じるほどの空、牛と羊が模様をつくる緑の草原。冬になれば白一色のなかに立つゲル、暖かいゲルの中の楽しい語らい。おいしいバターやチーズ、羊の料理。馬に乗って駆け回るこども。
しかし、ひるがえって考えると、デパートはない、ラジオはともかくテレビはない、映画もめったに見られない、学校は遠い、医者はいない、図書館はない、水道はない、トイレはない、ないないずくしじゃないか、ぼくらは、どちらが真実に近いかとまどう。
このヴィデオは、それはそうだが、と答える。もう少し知るべきことがあるのだと。
このヴィデオは遊牧民の四季の散文的な日常生活をつぶさにたどりながら、社会主義が崩壊したあと現れた経済の困難と、それを打開しようとする遊牧民の努力を描く。国家による搾取が終わったあと、流通過程を握った商人に収奪される姿を描く。それでも学校をつくり、失われた民俗芸能や手芸を復活させ、日常生活を豊かにしようとする女を描く。厳冬の家畜の出産にてんてこまいし、雨のない夏は飼料の不足をおそれ、多すぎれば羊の病気を悩み、家畜が順調に育てば喜び、羊毛が安ければ嘆く男を描く。
その映像が展開するなかで、羊の好む草や、ラクダの操縦法や、放牧地の畜群によってできあがった独特の植物生態、バターやチーズの製造法、去勢や毛刈りなどが自然に分かる仕掛けになっている。
山本 雅博 (47歳)
繊研新聞社 人材開発グループ
昔話になってしまうが、私がモンゴルのことに多少とも関わった頃には、モンゴルを実際に訪問したことのある人は少なかった。その頃、モンゴルと関わりのない人と話をしていて一番多かった偏見は、「モンゴル、ああ中国の奥地ね」「遊牧っていうのは、砂漠のなかを牧草を探して、あてどもなくさまよい歩いているんだ」というものだった。私自身もモンゴルに行ったことはなく、熱心に勉強したわけでもないが、偏見は見過ごせず、前者は論外として「遊牧は季節の変化に対応して合理的に組み立てられているもので、あてどもなくさまよい歩いているわけではない」とうけうりで話したものだ。
この映像では、一年間の遊牧の実際が四季を追って丹念に紹介されている。食料を確保するための屠殺など、ややショッキングだが、興味深いシーンもとり込まれている。海外旅行者は全体では減っても、モンゴルは増えているという事実が示すように、その素晴らしい大草原の映像と、小貫監督が相当のこだわりをもって描くホルショー結成の経過などを織りまぜて、全体として現代モンゴルの実像に迫っていく。7時間40分の映像を見るという機会はそうあるものではなく、上映開始当初は、残り時間が気になったが、実際にはテンポよく映像が流れ、エンディングの時には、なんだか自分も1年間モンゴルにいたような心地よい余韻がのこった。
今岡 良子 (35歳)
大阪外国語大学 講師(遊牧地域論)
英語の“consume”(消費する)という言葉の意味を同僚が教えてくれた。それは「食い潰す」というラテン語が語源なのだそうだ。
第2部の上巻の終わりで、遊牧民ツェンゲルさんたちは首都ウランバートルへ出かける。協同組合を設立した彼らには、畜産物の流通を確保するという切実な使命があった。ここではツェンゲルさんの表情の変化に驚かされる。最初、彼の顔はこわばっている。首都と遊牧社会の格差の大きさ、しかも市場経済は冷酷に彼らの行く手を阻む。傷心の帰郷。
しかし、故郷の東ボグド山が見えると、仔ヤギに与える柔らかい草を一心に摘み始める。ようやく家にたどりつき、家族とのふれあいの中で笑顔が戻る。担ぎ屋の持ち込む商品であふれ、とめどないconsu-meに精神までも疲弊する都はもう我々の都ではない。家畜と家族と仲間に根ざした協同組合を拠点にしてやり直せばいいんだ。ツェンゲルさんは、心の丈を高くして、さわやかに笑っている。その安堵感が見る者の心も解放してゆく。
このような内面の変化を映像におさめた撮影者の腕、また長編作品の折り返し点に再生と自律を取り戻す人間の姿をもってきた編集者の構成力、どちらもツェルゲルの大地に根ざしているからこそ発揮できた力であり、このドキュメンタリーの感動的なシーンの一つである。
ツェンゲルさんはブラウン管を通して私たちに問いかける。「あなたはconsu-meの世界にいるのですね?」私たちはあまたの生命、人類の平和、地球の資源の食い潰しに拍車をかけている。
また、繰り返される楽曲と朝夕の山羊の群れの動きは私たちに問いかける。「あなたも再生と自律の模索をしてはいかがですか?」終焉の警鐘が鳴らされていても、どの時点でどう歯止めをかけるべきかわからない。せめて、彼らに学び、顔と顔の見える範囲の人間関係と、手ずから生み出す生産と生活を尊重し、consumeに顔をこわばらせることから始めよう。そして、「食い潰しへの小さな抵抗」の輪が広がるよう、この作品の上映運動を応援したいと思う。
松岡 正喜 (49歳)
大阪・北陽高校教諭
とても長い映画であった。でも、フィルムにならなかった元の分を入れると、もっと長かったのではと想像している。
観ていて、自分も飛んでいって彼等と起居をともにし、生活の実際に浸かってみたいと思った。私たちの世界にある不条理で、猥雑なものがツェルゲルの村にはないように思えた。厳しい自然環境の中で、健康と家族の結びつき、それとわずかな友人と地域の交流のみが、生産と生活を支えている。誠に簡素だ。
だからこそ、他からの冗雑を必要としないのだろう。例えば、それは羊の屠り方に凝縮しているように思った。
一滴の血も出さず、一片の肉も無駄にしない羊やラクダの屠り方は、自然の厳しさが規定する生産の形態、そこで暮らす人々の人間の関わり方が長い年月をかけて作り出した文化なのだろう。
ソ連崩壊後の市場原理オンリーの経済原理が、かつての「社会主義」の国々において、成金マフィアという形で跳梁跋扈しているが、ウランバートルの論理を見据えてそれに翻弄されない地域的・自主的な共同を作っていくことが課題のように思う。
しかし、「言うは易し、行うは難し」だ。強制的なネグデルから自主的ホルショーへと、偉大な試みは始まったばかり。そのこと自体大きな前進かもしれない。心をより合わせ、仲間を誘い実験を重ねる時期なのかもしれない。
海のこちらに暮らす私たちも、もう行き着くところまで行った問題を山のように抱えているのだから……。
山口 幸二 (56歳)
立命館大学教授(言語学)
この映像の監督・撮影者である小貫さんは正直な人である。「制作現場からのメッセージ」(パンフレット素案)で、「この作品に対する自分の位置が微妙に揺れ動いている」と吐露され、それは制作の過程から編集の5年間そういう繰り返しであった、という。また「一般にこうしたことは、“表現”というもの本質から避けがたいことなのかもしれないが、このような繰り返しの鍛錬をぬきにしては、“表現”は成立しえないのかもしれない」とも言う。
思うに、このような「内省」なしに、いかに多くの民族誌的映画が無責任にも「遠くの他者」を創り出してきたことであろうか。小貫さんが苦しんだのは、わたし流の解釈では、他者(対象)と自分(表現者)との間にある「境界」の問題であろうと思う。自己の意識では乗り越えたつもりでも、表現の世界にある目に見えない「境界」に小貫さんは「ジレンマ」を持ち続けたのだ、と思う。
こういう内省をともなった小貫さんの「誠実さ」を、被写体側は直感的に感じとっているのであろうか。この長時間にわたる映像に「視る側」と「視られる側」(レンズを意識される場合も時としてあるが)といった厳然たる差異が見られないのは、わたしにとっては驚異的ですらある。
“いのち”という人間の根源にまでさかのぼったところから出てくる、いとおしさをともなった「人間としての連帯感」とそれをないがしろにする者への怒り……根本的にはそれなしにはこのような映像は産み出されないであろう。
7時間40分の上映会とそこでの新たな出会いや語り合いがこの作品をさらに豊かにしてゆくことを願って。
西山(萱野)亜希代(29歳)
社団法人 国際農林業協会
人間の本質は、慈しむことにある。
撮る人間も撮られる人間も、その眼差しはとても温かく、四季を通じた牧民の眼差しを写しだし、私たちの心を捉える。ツェンゲルさんの、我が娘を見るときのとろけそうな微笑み。山羊を追って走る子供たちの躍動感。組合成立時の参加者の顔の輝き。
家族を慈しみ、友人を慈しみ、土地を慈しむ。この温かな眼差しこそ、未来へ向けた第1歩となる。人々の幸せの根っこはここにあって、それはその土地に生きる人々が大事に守ってきた希望の種でもある。
いま、海外協力の片端にいて毎日を過ごす私にとって、このビデオは貴重な戒めを与えてくれる。価値観とは、人々自身が持っている。彼らから学ぶべきことは山ほどある。お互いが学びあう交流があって初めて、希望の種は私の中にも根付き、それはやがて私の生きる土地に蒔かれることになる。その時、彼らもともにその種を慈しんでくれるに違いない。
最後に、正直に言えば、このビデオは泣きたくなるほど懐かしく、私のモンゴル熱を呼び覚ましてしまった。今度の夏は、夫と幼い娘をおいて、モンゴルへ行く。いつか、娘がかの地を訪れる日を夢見ながら。
芝山 豊 (44歳)
清泉女学院短期大学 講師(比較文化・比較文学)
奈良県吉野の村の日常を描いた映画「萌の朱雀」を見る者に、おそらく、最も強い印象を与えるのは、主人公の祖母が見つめる山々であろう。その山並みを、われわれは、過疎の村に取り残されることさえ許されない老婆の目を通して見ているわけではない。その山々を眺める老婆を見つめる仙頭(河瀬)直美という若い映像作家の目を通して見るのである。
「萌の朱雀」の監督の3倍近い年齢の「新人」映像作家による「四季 遊牧 ツェルゲルの人々」でわれわれが目にするモンゴルの牧民たちの生活も、また、「あるがまま」の記録などという安直な素朴リアリズムとは無縁のものである。映像をとる者が、自分と対象との「他者性」を乗り越えてしまっているからだ。
それは、ひとつには、作家や編集者が登場人物たちの思想や行動に直接参与していることによるのだが、もうひとつには、見られる側の人々(ツェルゲルのモンゴル人たち)が見る側、つまり映像の作り手たち、(そして、ひょっとすると、観客をも)をその内面において見つめかえしているからに他ならない。我々は、モンゴルの人々の日々の営みを見ながら、モンゴル人によって見られている自分自身の「内なる辺境」をも見ることになる。
解説で、作り手が、「独自」な世界と呼ぶものは、決して、我々と異質な何かをさしているのではなく、むしろ、我われ自身の「他者性」を突き崩していくような、相互の関わりの中にあるのである。
映像に登場するモンゴル人の人々の生の讃歌とそのオプティミステイックな将来を短絡させることができないことをこの「新人」作家は誰より知り抜いている。だから、むしろ、この映像は時として、ペシミズムの濃い陰影に縁取られている。それでも、なお、人間を信じたいという思いが我々にせまってくる。それは一種の祈りだと言ってもよいのかも知れない。
それにしても、あの周防正行監督が「Shall weダンス」のアメリカ上映にあたり、「新聞に上映時間2時間16分と出てしまえば誰も見にきません。」といわれ、必死の攻防も空しく、約20分ものカットを余儀なくされたというのに、全6巻7時間40分を一挙に上映する「お弁当二つの上映会」を展開するという。よほど、気の長いモンゴル人だって、後込みするに違いない(酒がでれば別だが)。
スクリーニングだとか、マーケティングだとか、(採算という概念さえ)を徹底的に否定した「見てもらい方」はいかにも、小貫グループらしい。この新しい「時間に対する提案」に対して、どれほどの人たちが集まってくれるのか大いに楽しみである。 私は、いま密かに二個の弁当のメニューを考えている。
| △TOP |
この作品の第1次の試作品ができたのは、今からちょうど3年前であった。その年からはじめて毎年、私の勤める滋賀県立大学の「牧畜世界論」の授業の中で、この試作品を学生たちに観せては、レポートを提出してもらった。ここに掲載したものは、そのごく一部である。紙幅の制約上、全部を掲載できなかったのが残念である。
「今の若い者は……」という世評を尻目に、若者たちは意外にしっかりと自己と自己の周囲をみつめ、今日の状況から逃げずに、真剣に考えようとしている。改めて痛感させられたのである。試作の段階から完成への大事な3年間に、こうした学生たちからの支えがあったことをここに記して感謝したい。
今、深刻な問題として表面化し、その渦の中にいる日本の中学生や高校生が、この作品を見たとき、彼らと同世代の子どもたちが、自然や家族や地域の人びとの中にとけ込むようにして生きている姿を目の前にして、はたしてどのような反応を示し、何をそこから感じとるのであろうか。今はそれが知りたい思いである。
小原 さと子(人間文化学部・地域文化学科・アジア地域文化・2回生)
映像とはすごいものだと思った。本を読んでも、映像を見ても知識は頭に入ってくるが、本の場合、実際の情景をそのままの感覚として捉えることは難しく、自分の想像で補われることが多い。映像だと、動いて話して、実際のものが自分の中に直接入ってくる。私は、映像と本の両方とも大切なものだと思っている。しかし、今回のビデオで私がますますモンゴルに魅力を感じたことは確かだ。
岸本 正樹(同上・日本地域文化・4回生)
山々の風景の時に流れる音楽がとても映像とマッチしていて、心に響いてくるようだった。……映像を見てきて、その中で以前まで自分が抱いてきたモンゴルの像はどこかへ行ってしまい、まったく新しいモンゴルが僕の中で出来上がった。
熊谷 美絵(同上・アジア地域文化・3回生)
自分から何かをやって何かを変えていこうとすることが、なかなかできない私には、ツェンゲルさんたちは、とても生き生きしているように思えました。……ツェルゲル村に住む1人1人が本当に自分たちのために一生懸命話し合い、行動しているのだと思いました……。
ツェルゲル村の人々は、遊牧民共同組合ホルショー結成会議でも、ゲルの中に大勢集まり、自分たちの意志で自分たちの代表を決めるなどと、本当に、生き生きしていました。
中村 百合子(同上・4回生)
ツェンゲルさんがネグデルをぬけて、ホルショーを独立して作ろうとする時に、「ここに生まれ、育ったもの達が、ここで生きていくためのものを作っていくのは、当然のことだ」というようなことを言っていました。すごく格好いいなと思いました。日々、モンゴルの大地と共に暮らしていく。その美しい大地が私の頭の中でバックにあり、その中にツェンゲルさんの言葉が入ったからでしょう。
栗本 あきつ(同上・2回生)
「遊牧」のビデオは他のドキュメンタリーなどの番組と違って異彩を放っていると感じたのは、知っている先生たちが製作・編集しているということだけではなかった。それは、アルタイ山中ツェルゲル村に住む人々の、特にツェンゲル家、アディアスレン家の生活の形態、家族観や人間観などに深く関わっていて、出てくる人物に感情移入していくことで共感したり、日本との生活、人間観の差異、家族の関わりを自分と照らし合わせて感じ取ることができたからであったと思う。
北川 太郎(同上・2回生)
ツェンゲル家の奥さん、フレル家の奥さん、アディアスレン家のトゴスさん、ツェベク家の奥さん、いずれにも共通しているのは「強い責任感」と「並外れた行動力」それと「貧しさを感じさせない心のゆとり」だと思いました。……モンゴルの女性は聡明で機転が効き、その行動力は父親のそれもしのぐほどだという印象です。彼女たちが強い母に見えるのには、そうした「強さ」の裏に「ゆとり」があるのだと思います。先進国の母親は上を見て文句ばかりを言い、子どもをせきたてる傾向があるようですが、彼女達モンゴルの母は、今の幸福を感謝し、精一杯生きているから「ゆとり」がある母親・強い母親に見えるのでしょう。モンゴルの女性は日本の女性にはない「真の強さ」を持っていると感じました。でもことによると日本の女性は戦争が終わって、豊かになったから変化したのかもしれません。「豊かさ」と引きかえに「心のゆとり」がなくなって「欲」がでてくるというのは忌まわしいことと思います。
西田 亮介(同上・2回生)
人間同士だけでなく、人間と動物の「つながり」も興味深いものがあった。ヤギや羊を含めた五家畜と呼ばれる動物たちとの関係や、人々のそれらの動物への思い入れの強さは、われわれにはなかなか想像がつかないものであるように思えた。
椎屋 介士(同上・2回生)
最初ビデオを見始めた時は、どうなることかと思ったが、見はじめると、おもしろかった。……モンゴルのゲルはさすが遊牧の民という感じで、一つの無駄もなく、少ない資源を有効に使っているという感じがした。一見、人々はその日ぐらしという感じをうけるのだが、ちゃんと計画があり、秋から冬へと移動する時期も考えていたりしておどろいた。
安田 直己(環境科学部・生物資源管理学科・3回生)
春の草が少ない時期にツェンゲルさんの弟のフレルさんが、家畜を連れて家を離れることや、ツェンゲルさんが皮ひもを作っている作業、冬と夏では郡中心地でさえも人間が移動すること……。また、首都ウランバートルからの帰り道で仔羊のために草をむしっている姿、そこに見られる家畜への想いは私には新鮮ささえ感じさせた。
……夏には大地に芝生が生えたように緑で覆われることにも驚きを隠せなかった。早春の乾いた土ぼこりの立つ大地からは想像できない光景である。
永坂 朋子(人間文化学部・地域文化学科・アジア地域文化・2回生)
ドラマ仕立てにしてあるというわけでもなく、ただ淡々と人々の生活する様を映した映像というものは、現代っ子である私にはもの珍しいものであった。
特に印象深かったのはラクダのこぶを切り取る一連のシーンである。……あんな脂肪の固まりであるとは。ナイフで皮が薄く剥がされていく場面は、現場の人々の息づかい、肉の繊維が切られていく音が視覚を通して「聞こえた」気がした。……最も私と映像の中の人々が近づいた瞬間であった。そして現われた白い固まり。……何もないような大地の上にしっかりと息づいているいのちの「固まり」を見たと思った。
伊藤 佳代子(同上・3回生)
乳製品製造のところには感動した。……家畜から得られるものはすべて乳でも肉でも、感謝して、大切にいただく。私たちは……食事を食べられることに感謝するのも忘れ、平気で残したり、大量生産し、食べ切れないものは捨てていく生活です。人間は、誰の、何のおかげで生きていけるのか、……何をえらそうに生きているんだろうと思えてくる。私たちはこのへんのところをもう一度考え直す必要がある。
熊谷 健司(同上・2回生)
彼らは羊やヤギを搾乳するだけではなく、食肉用として、自らの手で殺し、肉を切っていました。……「かわいそう」とか「ざんこくだ」とか思ってしまいます。しかしそれはそういう場面を見ていないのにもかかわらず、肉を食べている私の自分勝手さからくる感情であるのだなと感じます。しかし一方、そういった生と死の場面を子供のころから見ているモンゴルの人たちは、その生と死ということを体で感じとり、しっかりとわかっているのだろうなと思います。
柾木 摂(同上・2回生)
冒頭に大阪の街がでてきたが、大阪出身の自分にとっては全く見慣れた光景であったが、それは遊牧という言葉からは想像もつかない光景でもある。遊牧・モンゴルという言葉を対照に大阪の街を見れば、この雑然とした街が様々な問題を抱えている事が、ありありと分かる気がした。これは大阪のみならず、世界の大都市・文明社会にもいえる事だ。
近藤 利起(同上・2回生)
モンゴルの人々は、なぜ、この文明が栄え、日本のような国が存在する中で、都市で暮らさず、あえて、この厳冬の中で生活をするのだろうと考えてしまう。寒ければ暖房器具で暖かくすればいい、食べたいものがあればお金をもって、コンビニへ昼夜を問わずに買いに行けばいい、そんな日本の暮らしは、現在の私にとっては、もうしぶんのない暮らしだ。……モンゴルの人々は、とても心が奇麗だと思わせる、本当に輝いた目をしている。でも、その生活は現在の私には考えられない。自分の心の中で大きな矛盾が生じていることがよくわかる。
高澤 悠介(同上・4回生)
モンゴルという国をありのままに描いている、という姿勢が、とても新鮮に感じられました。モンゴルを紹介する場合にありがちな作品として、モンゴルのことは何も知らない文明人である日本人がのびのびと生きる遊牧民の生活を堪能する様子を中心にして、つまり遊牧の理論よりも、都市生活にはない生活の豊かさばかりを描いているものが多いと思うのです。その点でこの作品はツェルゲル村という一地域を中心としながらも、モンゴル遊牧民全般に言える問題や遊牧を行う上での厳しさ、という専門的ではあるが、考えさせられる問題を映像を通して解りやすくなっています。おそらくこれは日本で初の試みではなかろうか、と勝手に考えてます。
小川 加世子(同上・3回生)
今、遊牧地域と都市との均衡のとれた発展、遊牧民と都市労働者の所得格差の是正などを図るにふさわしい国土利用計画があらためて問われてている。日本とは生活様式や地域環境が全く異なる国だけれども、現代文明が引きおこす物欲の支配によって、自然の生態系が積み木のように壊れやすいことは同じである。
北村 綾子(同上・日本地域文化・3回生)
私が見ているのはモンゴル・ツェルゲル村のビデオなのに、見ていると滋賀県の琵琶湖とその周りの生活のことと思いが重なってきます。いい生活、いい社会ってどういうものだろう、自然と人間って、どういう風に生きていったらいいのかな、このビデオから何かがわかりそうな、また解けない難問を出されているような、色々なものを受け取ります。 ……悪循環がつづいて「ネグデル」は崩壊して、本来の良さや力が失われていくのを見て、琵琶湖を見る私も同じことを考えます。その地域特有の自然と、そこで生活する人間と、分離するのもおかしいことで、ひとりひとりはそう思っているのに集団の意志となるとまたちがってくる、というのもおかしな話です……。
地域と、そこにいる人間はどう共に歩んでいったらいいのかな、と私は自分の足元を考える大切なきっかけを与えてくれたのが、この時間だった。
藤岡 紀子(同上・アジア地域文化・4回生)
遊牧をしている人たちはどこか農耕をしている人たちと似ていると思います。一日仕事をして、家族が協力し合って、マイペースに自給自足をする。いそがしくてもどこかのどかで心があたたかい人たち。食物生産に直接、従事しているという点でどこか通じるところがあるのでしょう。ただ、ツェルゲル村では高齢の人にもちゃんと仕事(役割)があって、敬われ、大事にされているようで、居場所があるようでしたが、最近の日本では農家であっても、お年寄りはあまりそういう風に扱われることは少ないです。
ツェルゲル村の人たちをビデオを通して見て、うらやましいと思ったことが幾つかあります。……大自然の中で生活できる、これはとても素晴らしいことだと思います。……日本には山も川も森林もありますが、……人の生活の場は自然とはたとえとなり合っていても触れあっている訳ではないのです……。
……私たちの社会は開発が進み、経済が大きく成長し生活水準が高くなった分、人と人とのつながりがうすくなったように感じられます。誰か困っている人がいても自分には関係ないと見ないふりをしたり、近所に住む人の顔も知らなかったり、人に迷惑とわかっていることでも平気でしたり。心の冷たい人、貧しい人が増えています……。
ツェルゲル村の人たちのように、大変なことはたくさんあっても、これから自分たちの社会をつくっていくパワーのある人たちは、心が豊かで力強いです。人と人とが助け合って色々なことをやっていく、それは人として非常に幸福だと思います。
……ビデオの完成版が出来上がったら、ぜひ試写会か何かで見せて下さい。
加藤 亜里(同上・日本地域文化・4回生)
ツェルゲルにおいて、人々の交流とは“情報の収集”であり、“地域”であり、決してうざったいものではありません。どうやって厳しい自然条件を乗り越え、生きていこうか、という生活への問題、あの人は元気にしているだろうか、というお互いへの気配りを示しながら協力して生きています。私は、そんなツェルゲルにおいて、「地域」のあるべき原点を見たような気がしました。
成田 卓巳(同上・アジア地域文化・3回生)
第2部は非常におもしろかった。ウランバートルに行った時の村の人たちのとまどいといったものが良くでていたと思うし、帰ってきた時、細い枯草を摘むシーンなどはとても感動的だった。そしてそれに続くあたたかい家族の風景は、古典的ではあるけれども十分にモンゴルの遊牧民の生活、家族関係をだしていると思った。正月の場面では、新年を迎える、そわそわしたようなあの独特の空気は、どこも同じなのだと思った……。
……今回(第3部)のビデオは、これまでのドキュメンタリータッチだった前回よりも、造り手の思想が感じられるものだった。広大な自然はそのままだったけれども、特に最後の語りの部分では考えさせられるものが多かった。日本のような先進工業国の生活にどっぷりつかっていると、農業や漁業で生計をたてている人達は、ずいぶんと厳しい生活を送っていると思いがちだが、本当にそうなのだろうか。……画面から伝わってくるのは、豊かな表情と、ゆったりとした生活だった。遊牧というのは生産効率という面からいえば、近代的な農業から見れば、とるにたりないものかもしれない。しかし、……スタイルをほとんど変化させずに今にいたっているのには、何らかの真実のようなものがあるのだろう。
矢守 永生(同上・3回生)
この巻(第3部下巻)には、いたく心を動かされた。後半のアディアスレンさんの語りや、狩りへ行ったときのツェンゲルさんたちの語りを見てである。……彼らがどんな生き方を求めているか、何を考えて日々生活しているかということを……ここにきてやっと自分の目で見、感じることができた。(彦根市)八坂町を歩いていて、おじいさんやおばあさんと話をした時のように、胸がジンとなった。
一之瀬 奈美(同上・3回生)
映像や語りがとても主観的だったので、すっかりこちらもつり込まれて、最後の別れのシーンや回想シーンでは「ああ、これでさよならなのか」と淋しい気持ちがした。ビデオをまわしていた人や語っていた人たちの遊牧民に対する深い思い入れがなければ、きっと単に「あ、おしまいね」と思うだけだっただろう。遊牧民の心のやさしさ、彼らとの交流の輪の中に私まで入っているような気がした。もう一度ツェルゲルの人たちに会いたいと思った。
青山 真久(同上・3回生)
エンディングの「そこに大地がある限り人は生き続ける」という言葉には、ジーンとくるものがあり、涙が出そうになった。
草川 恵仁(同上・2回生)
考えてみれば、自分の食べる物をつくらずとも生きていける私達の社会は、不思議なものだなあと思いました。もし、食べ物が売られなくなったら?という不安もなく、毎日生活している自分も、特殊な状態に置かれているんだと気づきました。自分の食べ物も自分で作れない……というのは、なんだか不安なものだなと思いました。都市とかができていく上で分業が起これば、「あの人にはできるけど、この人には出来ない」ということがでてきてもおかしくないですが、長い間伝えられてきた技術など、私は何も受け継いでいないような気がして寂しいです。
野口 洋(同上・2回生)
……「ホルショー」という新しい協同体を作りだそうとしていたツェンゲルさんたちの視野の広さ、世界観に感心した。国家に逆らってまで自分の信じる道をゆくのは本当に勇気がいることであろうし、しっかりとした信念さえあれば、村の仲間も賛同してくれる。情報がうもれて、ありあまって、世界中の事件を瞬時に知ることさえできる私たちよりも、モンゴルの砂漠に住んでいるツェンゲルさんの方が、世の中の流れをしっかりつかんで、的確な判断で自分の人生を生きている姿を見て、少しはずかしい感じさえした……。
1・2部と見終えて、自分が最も関心を持ったことは、“社会”特に“地域社会”とは何か、ということである。
僕の住んでいる地域社会はいわゆる新興住宅街で、約200戸の世帯がある。近所づきあいがあるのは、“向こう三軒、両どなり”のみで、2軒先きのとなりはすでに名前と顔が一致しない。
その一方で“どこどこの誰さんの息子さんは何々大学に合格した”とか“あそこの家はどこどこの会社に勤めている”とかいうような、“イヤ”な情報ばかり早くまん延する。
それに対してモンゴルでは隣人は何?先ということがあっても、何かあれば、助けてくれる。農耕民と遊牧民という違いがあるにせよ、そういう関係を構築しているツェルゲルの人々をうらやましく思った。日本の地域社会は「物理的に近くても精神的に遠い」という感じがしたが、ビデオから感じるツェルゲルの地域社会は「物理的に遠くても精神的に近い」という印象を受けた……。
ホルショー誕生のプロセスを見ていて、僕の地域社会にある“自治会”との悲しい違いを実感してしまった。
自治会とホルショーを同じウエイトにしてしまうのは、強引なことではあるが、共同体や地域社会の本当の意味(必要だから、作る、生まれる)を思い知らされた……。
第3部を残すのみとなってしまったが、もう少し、社会の枠?家族、地域、共同体について考えてみたいと思う。
水谷 玲子(同上・3回生)
印象的だったのは、遊牧民のための組織であったはずのネグデルがその役割を遊牧民のために果たしていないから、自分たちで納得のいく共同組合を作り出そうとツェンゲルさん達がほん走していたことです。そしてツェンゲルさんは35歳です。とても35歳には見えませんでした。ほかの人達もそうです。それは決して老けているとかいうのではなくて、とてもいい顔をしているのです。いろんな経験をして自分達自身で生活をしてきたという、きりっとした意志の強い顔です。私が35歳になり、あんな素敵な顔になれるのかは疑問です。
そしてホルショー結成会議の場に70人もの人々が広いツェルゲル村から集まってきて、議論をかわしているのを見て、どうしてこの遊牧民の人々はこんなに一生懸命になれるのだろうと、不思議に思いました。私達は何か新しいことをしようとすると関心を全く示さなかったり、めんどうなことは困るから何もしなかったりする人が多いことと思います。なぜこう違うのかと考えると、遊牧の人々はその日その日を精一杯生きているからではないかと思います。燃料……水……。遊牧民は1つ1つが大切なのを身を持って知っている、そうやって小さな頃から生きてきているから、自分達の生活を少しでもよくするためには、現状に甘えず、自分が動かなければににも始まらないとわかっているんだと思います。私はいろんな議論をかわしたり、友人同志でおしゃべりをしたり、さく乳したり、何をするにもいきいきとしていた人々の顔が忘れられません。
……あのツェルゲルの人々のように、1人でも多くの人がいい顔になることが大切だと思う。そして、それは心がけ一つでそれへの一歩がすぐにでも踏み出せるはずである。ツェルゲルの人も私達も同じ人にはまちがいないのだから。
……この全巻のビデオを通して、私たちが毎日少しずつ忘れていってしまっている何かを模索していくことができると、私は思う。
井上 一(同上・2回生)
最初に驚いたのは、モンゴルの雄大な大自然、そして、そこで力強く生き抜いている人々の姿であった。極限の環境であるにもかかわらず、人々は気さくで、子供たちも素直だった……。
僕たちは物の溢れた時代に生まれ、それを当たり前のこととして育ってきた。そういう僕たちにとって、モンゴルの遊牧の生活は考えさせられることが多い。大人から子供まで仕事を分担して家族で支え合う生活は素晴らしいことだと思う。家族は学校の機能を備えているという話があったが、まさに、これこそ、今の日本に必要なことのように思える。僕は比較的田舎に生まれ、古い風習の中で育ってきた。幼いころから親に、「働かざるべき者食うべからず」といわれてきたが、そのことが今よくわかる。この大学に来てから、自分が田舎に生まれたことに誇りを持てるようになった。以前は都会の暮らしに憧れていたが、今は地元が一番と思えるようになった。
ツェルゲル村の人々の生活を見ていると、やはり人生は金だけではないということに気づかされる。豊か・貧しいに関係なく、皆いきいきとしていて、しっかりと現実を見据え、淡々と生きている。僕たちは、時間とお金があり余りすぎているから、現実から逃避しようとしてみたり、非現実的な行動に走ってみたりしてしまうのではないかとさえ思えてくる。ツェンゲルさんは、35歳という若さにもかかわらず、村の人々のために働き、ホルショーの結成に取り組んでいた。僕たちも、この若さを、もっと良い方向に使えるはずである……。
僕自身も、表面だけでなく、深みのある温かい人間になりたいと思う。
| △TOP |
